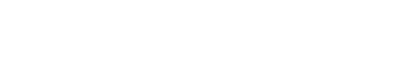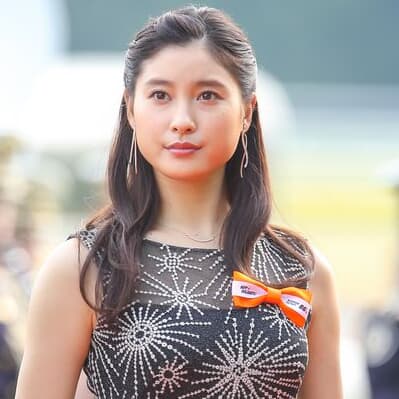「ゲス不倫にアナーキズム、ヘンなガイジン、ヌード、日銀。事始め人の退場劇」1923(大正12)年 1924(大正13)年【連載:死の百年史1921-2020】第3回(宝泉薫)
連載:死の百年史1921-2020 (作家・宝泉薫)
死のかたちから見えてくる人間と社会の実相。過去百年の日本と世界を、さまざまな命の終わり方を通して浮き彫りにする。第3回は1923(大正12)年と1924(大正13)年。近代日本の事始めに関わった人たちのそれぞれの「退場」を振り返る。

■1923(大正12)年
百年前のゲス不倫は心中で終わった
有島武郎(享年45)大杉栄(享年38)
大正12(1923)年は、関東大震災の年だ。その15日後には、混乱する東京で陰惨な事件が起きた。アナーキストの大杉栄が、内縁の妻・伊藤野枝や6歳の甥とともに連行され、憲兵の甘粕正彦らによって殺害されたのである。
また、震災の3ヶ月前にはもうひとつ、世間を騒がせる事件が起きた。文学者・有島武郎の情死だ。彼は7年前に妻と死別したあと、独身だったが、人妻と恋におち、その夫から脅迫されるなどしていた。相手の女性は、創刊まもない『婦人公論』の記者・波多野秋子。「眼のひかりが虹のように走る感じの人」(室生犀星)という美女で、永井荷風や芥川龍之介にも気に入られていた。

ただ、今でいうメンヘラ気質で、そこがこの時期の有島には魅力的だったようだ。というのも、死の3年前、彼は評論『惜しみなく愛は奪う』を発表して、こんな哲学を語っていた。
「若し私が愛するものを凡て奪い取り、愛せられるものが私を凡て奪い取るに至れば、その時に二人は一人だ。(略)だから、その場合彼が死ぬことは私が死ぬことだ。殉死とか情死とかはかくの如くして極めて自然であり得ることだ」
そんな哲学を実験できそうな相手が、波多野だった。有島は友人でもある出版社社長に「実は僕らは死ぬ目的をもって、この恋愛に入ったのだ」と明かし、姿を消す。そして2日後、軽井沢の別荘で心中を遂げた。遺書にはこんなことが記されていた。
「私達は長い路を歩いたので濡れそぼちながら最後のいとなみをしている。森厳だとか悲壮だとかいえばいえる光景だが、実際私達は戯れつつある二人の小児に等しい。愛の前に死がかくまで無力なものだとは此瞬間まで思わなかった。恐らく私達の死骸は腐爛して発見されるだろう」
ちなみに、白樺派の作家を研究する生井知子は有島の自殺願望を「幼児退行的なもの」と見なしている。父親による厳格すぎる教育によって「精神的外傷」を負い「自らを無用の存在」と感じるがあまり、子供のように甘えたい、それが無理ならいっそ死にたいという「誘惑に身を委ねてしまった」というわけだ。
この見方には共感するが、世間の反応はもっとミーハーだった。波多野を「魔性の女」として叩いたり「死に進んだ勇気」を賛美したり。また「人の女房と心中する 有島病気が流行し(略)これが純真の恋というなら困ったネ」(『困ったネ節』)という歌がうたわれたりした。
なお、有島はアナーキズムにも関心を抱き、大杉栄を支援してもいた。最期のかたちは違うが、ともに時代を代表する知識人の挫折だ。震災が起きたこの年を境に、日本の運命は傾いていったとする見方ものちに生まれた。