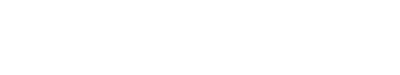「仕方がない」という諦めか。「行動あるのみ」とする覚悟か
覇王・織田信長の死生観 第7回
本能寺の変で突然の死を遂げた。
最期まで自ら槍を取り戦った信長の人生は
命知らずの破天荒なものだったのか?
信長は死をどのように捉えていたのか?
そして、ついに見つからなかった死体の行方は?
未だ謎多き信長の人生と死に迫る!

「これは謀反か、いかなる者の企てぞ」
信長の問いに応じて本能寺の外の騒ぎを確かめた森乱(蘭丸)は、それが光秀の謀反であることを信長に伝える。この時信長は、ひと言「是非ひに及ばず」と言ったという。
この「是非に及ばず」というフレーズは、これだけで本能寺の変を表わすほど有名になっている。それでいて、そのひと言をめぐる解釈は定まっていない。ある研究家は「仕方がない」という諦めの言葉とするし、別の研究家は「是非を論じている場合ではない、行動あるのみ」という意味にとらえている。
この時の信長のひと言を諦めの言葉とするのは、「人間五十年」や「死のふは一定」を愛唱したという信長の死生観に関連させた解釈であろう。しかし、そこまで強引に結び付ける必要はあるまい。なぜかというと、「是非もない」「是非に及ばない」という表現は、当時にあってはごく一般的なものだからである。要するに「ここでどうのこうの言ってもはじまらない」ということである。つまり「是非を論じている場合ではない、行動あるのみ」とするほうが的を射ていると思う。
大久保彦左衛門の著書『三河物語』には、寺外の騒動に驚いた信長は、「是非に及ばず」ではなく、次の言葉を発したと書かれている。
「上之助(城介)がべつしん(別心)か」
「城介」とは長男の信忠のこと。前夜遅くまで父と一緒に過ごしており、この時、600メートルほど離れた妙覚寺に宿泊しているはずである。信長は一瞬、長男の謀反かと思ったというのである。『三河物語』は、信憑性において『信長公記』より数段落ちる。はっきり言って信じるべきではない。ただ1つ、次のことだけは言えるだろう。
信長の時代から40~ 50 年たっても、彦左衛門には次のような意識が頭の片隅に残っていた。信忠というのは、父の信長をも脅かしかねない存在だった、という意識である。
<次稿に続く>