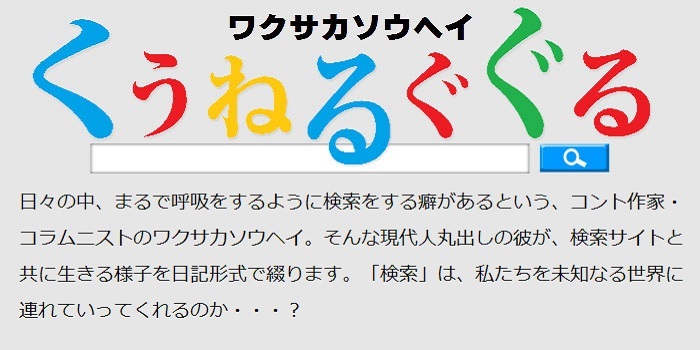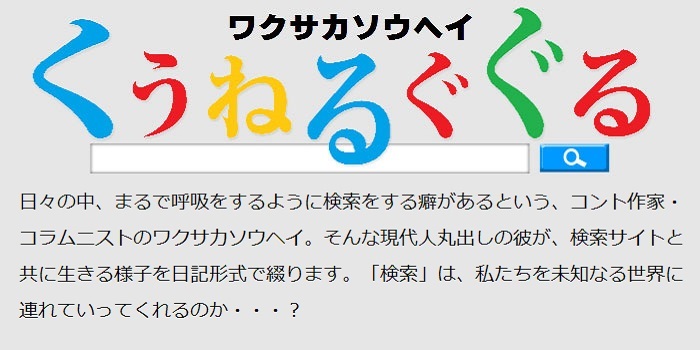第45回:「キスマーク」
<第45回>
8月×日
【「キスマーク」】
これは、僕が唐突に欲情に駆られて、狂ったようにグーグル検索をして、そして最終的には「ぎゃあ」と叫んでもんどりうつまでの、読んでもビタ一文得はしない、とある夏の一日の記録である。
電車に乗っていた。
僕は、文庫を開いていた。
向かいのシートには、二人組の男子高校生が座っていた。
チラっと目をやる。
補修授業でもあるのだろうか、夏休みの時期だというのに二人とも制服を着ていた。
すごーく、地味ーな、いけてなーい、男子高校生たちだった。
ひとりはメガネをかけていた。
アメリカ人がその子を見たら開口一番に「Wow! オイリー!」と叫ぶこと間違いなしの、油にまみれたメガネだった。一瞬「シーチキンなのかな?」と勘違いしそうになるほどに、そのメガネには油がしたたっていた。「いっそ、かけないほうがよく見えるのでは」とアドバイスしたくなるほどに、そのメガネは油で曇っていた。そんなアブラメガネの彼は、さらに坊主で出っ歯だった。顔面に要素が多すぎる。顔面で「要素のサマーソニック」を開催しすぎである。
もうひとりの彼は、打って変わって、無個性な顔立ちをしていた。
歯医者の待合室の壁、みたいな顔だった。
そして、ヒョロヒョロの身体をしていた。HPが「セミの幼虫」とどっこいどっこいなのでは、というくらいの虚弱な身体つきだった。
そんな彼は、髪型がスポーツ刈りだった。
絶対にスポーツとは縁遠そうな身体なのに、スポーツ刈り。筋肉隆々の男がいとうせいこうのような髪型をしているのと同じような悲哀がそこには漂っていた。
僕はその二人組にシンパシーを感じずにはいられなかった。
生まれてこの方、ずっと、「いけてなーい」人生を送ってきたが、特に高校時代の僕のいけてなさといったら、群を抜いていた。
僕もアブラメガネをかけていたし、髪型はスポーツ刈りを力づくで伸ばした「マジックマッシュルームカット」としか言えない代物だった。
無論、モテなかった。
二人組の観察から再び文庫に目を落としながら僕は、自分の灰色の高校時代に想いを馳せていた。
「見てよ、これ」
アブラメガネのほうが、なにかを見せている声がした。
「うわ、すげえ」
スポーツ刈りが、感嘆の声を上げている。
「でも、ほら、オレだって」
スポーツ刈りが負けじとアブラメガネに見せ返す。
「ふうん、やるじゃん」
アブラメガネが余裕で受ける。
いったい、なにを見せ合っているというのだろう。
妖怪ウォッチのレアカードだろうか?それとも、お互いのニキビの角質?もしかして、ただ綺麗なだけの小石?
よすんだ、二人とも。そんなものを見せ合ったところで、君たちのいけてなさがぐんぐん地に向かって根をはるだけだ。
すでに二人組に過去の自分をぴたりと重ね合わせてしまっていた僕は、忸怩たる思いから彼らを直視することができず、頁の上の文字列に必死に集中していた。
「お前の彼女も、けっこういやらしいんだな」
え?
「お前の彼女こそ」
え?え?
「まあ、お互い、愛されてるってことだな」
なんだ?この二人、恋人がいるのか?
「まあな。でも、困るよな、こんなにいっぱい」
いったい、何を見せ合っているんだ?
途端に文庫の文字は踊りだし、僕はもう二人が見せ合っている「なにか」が気になって気になって、我慢できずに再び顔をあげた。
二人は、シャツのボタンを三つも開けて、互いの胸元に広がった赤い斑模様を見せ合っていた。
「キスマークなんてさ、親にバレたら恥ずかしいよ」
頭の中に「ジャーン」という、低いピアノの唸り、もしくはWindowsのシャットダウン時の音が、鳴り響いた。
ウソだろ、お前たち。キスマークだなんて。
言わずもがなだが、僕は30年の人生の中で、キスマークなどつけられたことなど、一度もない。
キスマークなんてものは、マスオさんが酔った勢いで行ったスナックでYシャツにつけられてそれをサザエさんが発見し「ンマー」と言う、みたいな長谷川町子美術館管理下のもとにしか存在しない、想像の産物に近いものだと思っていた。
それが、さっきまで仲間だと思っていたこの二人組の皮膚に、付着しているというのか?
ウソだろ。
キスマークじゃないと言ってくれ。本当はアトピーだ、と言ってくれ。
「そのキスマーク、いつの?」
「ん?昨日だよ、昨日」
「マジかよ。オレも昨日だよ」
二人組は、次の駅で電車から降りていった。
電車に取り残された僕は、妙な欲情を感じていた。
瞼の裏にこびりついて離れない、彼らの胸元のキスマーク。
そこに漂う、生々しい性の香り。
彼らは過去の僕だったかもしれず、だとすれば僕にもキスマークを恋人からプレゼントされるような別の人生があったのでは?というクソバエのような錯覚。
それらが混然一体となり、パープル色のムラムラとした想いが炎上していた。
だいたい、キスマークというものは、具体的にはどのように作るのか?
たまらず僕は文庫を投げるようにカバンの中にしまい、代わりにiPhoneを取り出し、「キスマーク」を猛烈な勢いでグーグル検索した。
キスマーク
腕やもも、胸元などの場所に口を付け、強く吸うことで、内出血により赤いキスマークができます。
ああ、そうだったのか。
あれは口紅で作るものではなかったのか。
だから彼らの胸元には、小さな内出血の跡が散らばっていたのか。
彼らが携えていたのは、正真正銘、キスマークだったのだ。
フラフラとした足取りで、駅を降り、朦朧としながら家路を歩いた。
ああ、神よ。
願わくば、我の身体に、キスマークを与えたまえ。
キスマークをしらないまま、死んでいくだなんて。
神よ、我にキスマークを!
玄関を開け、靴を脱ぎ、家へと上がった。
その瞬間、つんざくような激痛が足裏に走り、僕は「ぎゃあ」と一声叫んだ。
おそるおそる、足の下を見た。
そこにはなぜか、アブがいた。
足の裏は、アブに刺され、熱く腫れ上がっていた。
「違う、神よ、違う。僕が求めているキスマークは、こんなんじゃない」
痛みで涙がこぼれ落ちた。
「神よ、違う。虫じゃなくて、女性だ。針じゃなくて、唇だ。僕が求めているキスマークは、胸元にであって、こんな小汚いカカトにじゃない」
神は雑に僕の願いを叶え、雑な感じで去っていった。
僕は玄関先に膝をついた。
それと同時に外から雨音が聞こえてきた。
雨音もずいぶんと雑な感じで、僕はいつまでも薄暗い玄関先で立ち上がることをしなかった。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)