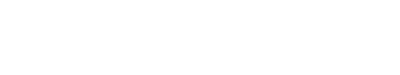織田信長の茶頭・津田宗及の危機管理
季節と時節でつづる戦国おりおり第329回
大通庵はなぜ建立されたのか?
今年の冬はさ・む・い! 洗濯物も凍り付く寒さの中、ちょっとお出かけして写真を撮って来たのはこちらです。

通りを挟んだ向かい側、歩道の際に建つ小さな石碑と説明板。これは、大通庵という寺院の跡を示すものです。

この大通庵、堺の豪商・津田宗及(天王寺屋宗及)が父の菩提寺として建てたもので、大徳寺の春屋宗園が開基です。
場所は堺市堺区熊野町の熊野(ゆや)小学校の南側で、中世堺の市街範囲の中。
宗園は黒田如水や石田三成とも親交が深かった名僧で、宗及は彼に息子を弟子入りさせるほどその関わりは密接でした。
言うまでもなく宗及は織田信長の茶頭としても有名な茶人ですが、その彼がこの場所に大通庵を建立したのはどういう意味があったのでしょうか? 実はそこにはかなり現実的な目的があったんじゃないかと思うのです。
1年半ほど前、このブログの第254回でご紹介しましたが、北側の熊野小学校の敷地内では中世堺の時代の堀の跡が発掘されました。
今、その跡は次の写真のように新校舎が建つなど整備されてその面影をしのぶことはできません。

そこで、かつて現地説明会がおこなわれたときの写真を再掲しましょう。

この濠をこのまま南に伸ばした右側が大通庵跡。つまり、寺は堺の濠のすぐ内側にあったということになります。そして、大通庵を西に進むと、大小路の東、宗及屋敷があったのではないかとされる場所に行き着きます。
宗及はその茶会記『天王寺屋会記』の他会記の永禄12年(1569)の記事で織田信長が堺に攻め寄せるため町はパニックになり、「堀をほり櫓をあげ」と防衛体制を固めるのに必死になったと書いていますが、この堀もその際に掘られたものかも知れず、また天正8年(1580)創建という大通庵自体も、町の東側を守る目的のために堀の内側に築造された可能性があるのではないでしょうか。宗及は“いざ鎌倉堺”という時、屋敷からすぐ東側へ人数を派遣し、大通庵と堀で侵入者を食い止めるという危機即応システムを構築していたのかも知れませんね。