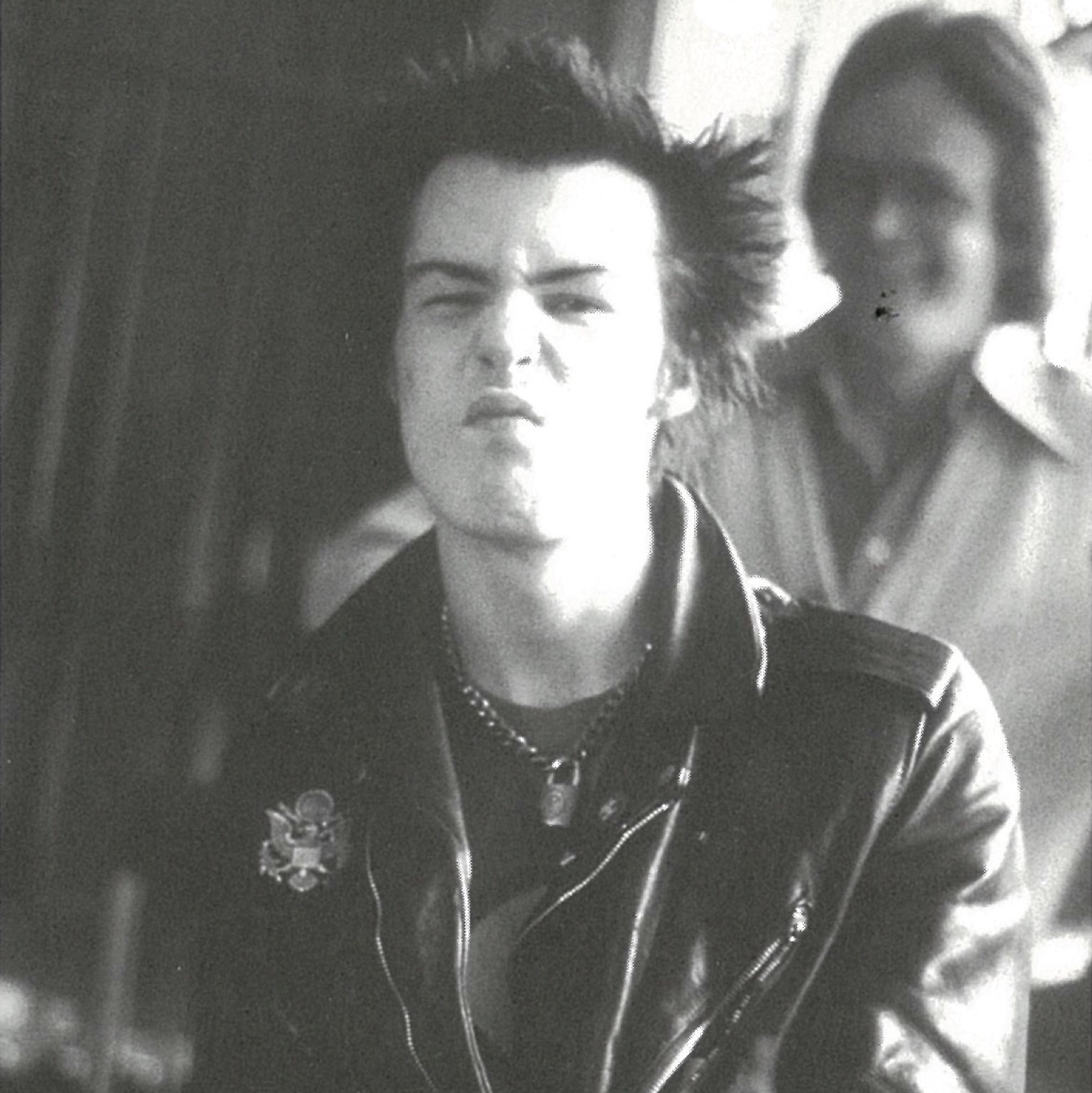美食家とは限らない? 文豪が愛した店に名店が多いワケ
文士と画家が愛した宿
“聖地”! 今なお残る文豪行きつけの名店

雑誌『一個人』2018年4月号の大特集は、「文士と画家が愛した宿」。あるときは、いまも名作として語り継がれる作品の舞台となり、またあるときは、作家にとって重要なキーワードとなる出来事が起きるなど、文豪を語るうえで欠かせない宿や店を紹介している。
マンガ『文豪の食彩』の原作者、壬生篤さんは、こうした店を多数巡っている。その楽しみ方を本誌でも紹介しているが、本稿では「なぜ文豪が愛した店に名店が多いのか」という疑問について考えたい。
文豪といわれる作家たちが活躍したのは、おもに明治から昭和初期にかけて。日本は関東大震災や太平洋戦争を経験し、街が壊滅状態になってしまった。そのため、当時の建物が現存していない場合が多いが、同じ場所で文豪たちが愛したメニューを提供し続ける店は少なくない。
その店の一例を紹介すると、谷崎潤一郎の随筆『蠣殻町と茅場町』には、人形町「玉ひで」が登場する。谷崎はこの店の「軍鶏すき焼き」を出張料理で食べたとみられている。玉ひでといえば、現在も親子丼が有名で、昼時には必ずといっていいほど行列ができている人気店だ。
ほかにも、ゆかりの店は名店揃いで、文豪たちはさぞ美食家だったに違いないと思わされるが、壬生さんによれば「必ずしもそうではない」とのこと。池波正太郎のように、食にまつわるエッセイなどを多数発表しているグルメ作家は意外と少なく、行きつけの店も、編集者などに連れてこられたことをきっかけに通い出したケースは珍しくないという。
また、ゆかりの店として伝えられる飲食店のなかには、残念ながら閉店してしまったところも多い。その理由はさまざまだが、今も営業している店は、真の実力のある名店だからこそ生き残れたとも考えられる。
文豪がある飲食店を利用したことを著書などに書き残していれば、その事実が永遠に語り継がれることになる。宣伝効果が非常に高く、店にとっての財産だ。これも、21世紀の現在もなお店が継続しているひとつの理由と考えられるだろう。そんな話も壬生さんからうかがった。
文中に登場する料理を食べることは、作品の世界観を広げるエッセンスとなる。今風にいえば“聖地”でもある、文豪ゆかりの店。本を読むだけでは味わえない体験を、多くの人に楽しんでもらえたら幸いだ。