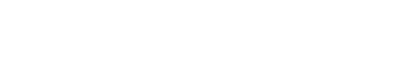謎の大王・継体天皇の擁立を推進したのは誰か
新説! 謎の大王「継体天皇」と王位継承の謎 第5回
3度遷都し、即位20年目に大和入りをした謎の大王「継体天皇」。その王位継承のミステリーに迫る連載、第5回。

継体天皇像/標高約100mの足羽山(福井県)、山頂にある足場山公園に立つ。継体天皇が越前三国で育ったという『日本書紀』の記述にちなんで大正年間に建てられた。
継体天皇の擁立は中央豪族が主導していた
見落としてはならないのは、次期大王の人選が大伴金村や物部麁鹿火など大臣・大連らによる合議で決定されたことである。継体の擁立は中央豪族主導だったことになるが、この『日本書紀』の記事は信じられるだろうか。確かに、近江や越前、尾張などの豪族連合が中央の政権から王位を奪い取ったのであれば、その後もっと地方豪族が躍進していいはずだし、政権の中枢もこれらの地に移ってしかるべきだろう。しかし実際はそうならず、継体は樟葉・筒城・弟国と摂津・山背を転々しながらも最後は磐余玉穂宮に入り、その後も都は大和を離れなかった。近江や越前、尾張を地盤とする継体だったが、直接には彼を大王に擁立したのは大伴金村や物部麁鹿火など中央の有力豪族だったとみるべきだろう。
継体が即位後も20年間、大和盆地に宮を置けなかったことをもって、大和盆地内に反継体勢力がいたのではないかとする説がある。おそらくその中心は葛城氏であったろう。かつてこの氏は雄略天皇の即位時に滅ぼされたと考えられてきたが、今ではその後も勢力は衰えながらも実力は残存していたとみる見方が定着しつつある。近年は、葛城地域の古墳の状況からも、6世紀前半くらいまでこの地に有力な前方後円墳が造られていたことが指摘されるようになった。
- 1
- 2