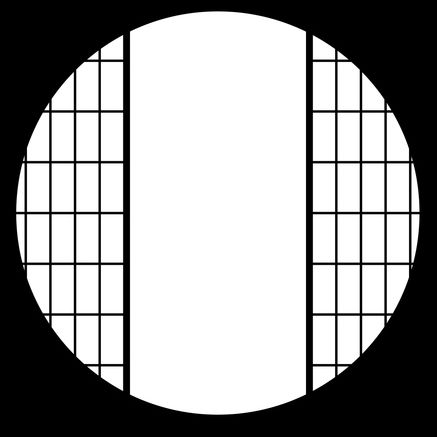「志ん朝」と「談志」。何が違ったのか?
大事なことはすべて 立川談志に教わった第8回
■「俺の理論も、あくまで仮説だ」
もし万が一、師匠が一旦確固とした「落語は人間の業の肯定である」という定義を金科玉条のように守るだけの人だったら、もっと長生きしていたに違いないと確信しています。むろん、当人はそんな安穏な生き方を猛烈に拒否していましたが。
「俺の理論も、あくまで仮説だ。俺を陵駕する理論、持ってこい。いつでも受けてやる」と、相手が前座ですら、ずっと言い続けていたのがそのなによりの証拠です。
今思うと、師匠は『現代落語論』の末尾に「落語が能のような道をたどる危惧」を記していました。そんな自らの理論にまるで好んで自縄自縛するSM嬢のように、「能のような道をたどらせてなるものか」という気概も込めて、自ら確立、定義した哲学すら進化、深化させてしまうのも師匠の魅力でした。
いや、「落語は人間の業の肯定である」という一番最初の理論を、より社会全体にも押し拡げ、より人間に寄り添った形で展開し、つなげようとしたのが「世の中の大半は虚である」という「唯虚論」なのでしょう。
そしてついには、そんな「落語の理詰め」を究極までに追及した人だからこそ、「理詰め」では解釈分析できない世界を描くという「落語の『世界最終革命』」を、晩年の「イリュージョン論」にみようとしたのでしょう。