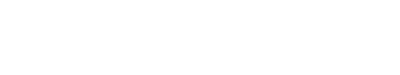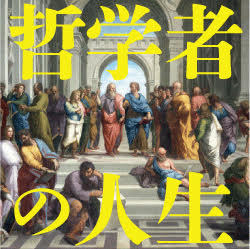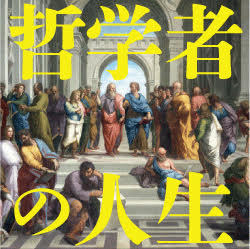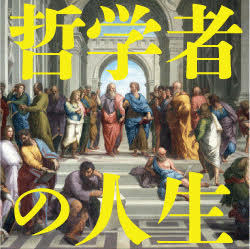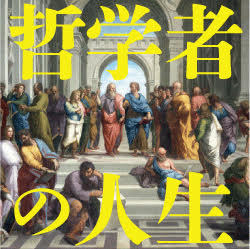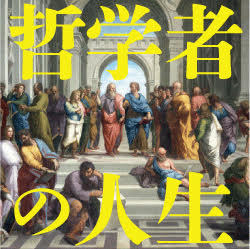古代ローマ哲人が考える「もっともよい復讐の方法」とは?
天才の日常~マルクス・アウレリウス篇
マルクス・アウレリウスもまた、衝動的な感情や、快楽を求める欲望を排除して、理性的で静かな生き方を送ろうとした。『自省録』は、自らの心の内に生じる乱れをなんとかして鎮めようとして苦悩する記述に満たされている。だが、ローマ帝国皇帝として、実務に追われ、多くの部下と関わり、権力闘争に巻き込まれ、不測の事態への対応を迫られる日々を送っていれば、心を乱さずに生きるのは不可能である。
『自省録』が長い時を隔てて多くの読者の心を打ってきたのは、哲学者として高く掲げた理想と現実との落差に翻弄されて、思うように生きられない自己に苦悩しつつ、それでも理想に向かって悲壮なまでに自らを叱咤し続ける、魂の内の対話が生々しく描かれているからだろう。
“善い人間のあり方如何について論じるのはもういい加減切り上げて善い人間になったらどうだ”
こんな言葉にも、高い理想に殉じようとしても思い通りに生きられずに苦悩する彼の思いが込められている。
最盛期のローマ帝国皇帝として、豪勢で奢侈な生活をおくることもできただろう。実際に、共同皇帝として同時に即位した義弟のルキウス・ウェールスはほとんど政務に携わることなく贅沢三昧の生活を送り、後を継いだ息子コンモドゥスは趣味の剣技を追求するばかりで暴政を敷いた。しかし、ストア派哲学者であるマルクス・アウレリウスは、欲望を満たすための贅沢には興味がなく、魂の静穏だけをひたすらに求め続けた。
そのため、彼の世界観や死生観は虚無的な趣がある。宇宙は理性によって支配され、人間も魂の内に理性を持つ。物質は原子によって構成され、自然の原理によって生成、分解を繰り返す。人間は広大で永遠の宇宙から見ればちっぽけで刹那的な存在に過ぎない。自らの肉体も、すぐに土に還り、宇宙を構成する原子へと分解されていく。
死について、次のように語っている。
“病人を診察した医者たちも皆死んでいき、不死身のように権勢を奮った暴君も皆死んでいった。墓に他人を埋めた者は皆、既に墓に横たわっている。これは全て、束の間の出来事である。昨日は少しばかりの粘液、明日はミイラか灰。だからこのほんのわずかな時間を自然に従って歩み、安らかに旅路を終えるがよい。”
“死は誕生と同様に自然の神秘である。同じ元素への結合、その元素への分解であって、恥ずべきものでは全然ない。”
彼が最期を迎えたのは、現在のウィーン近辺で、やはり遠征中の戦陣だった。伝染病に侵された彼は意識が朦朧とする中で「戦争とはこれほど不幸なことか」とつぶやいたとされている。
皇帝として多くの社会福祉政策を行っていたマルクス・アウレリウスは、死後もローマ市民から尊敬を集め、神として祀らることになった。だが、彼自身は死後の名声など一切気にしていなかった。
“遠からず君はあらゆるものを忘れ、遠からずあらゆるものは君を忘れてしまうだろう”
だが、たとえ彼の肉体が灰となり、原子に分解されて自然に還ったとしても、彼の魂が刻んだ文章は1900年以上経った現代でも忘れられることなく、読みつがれている。