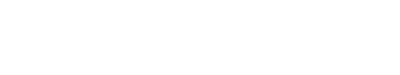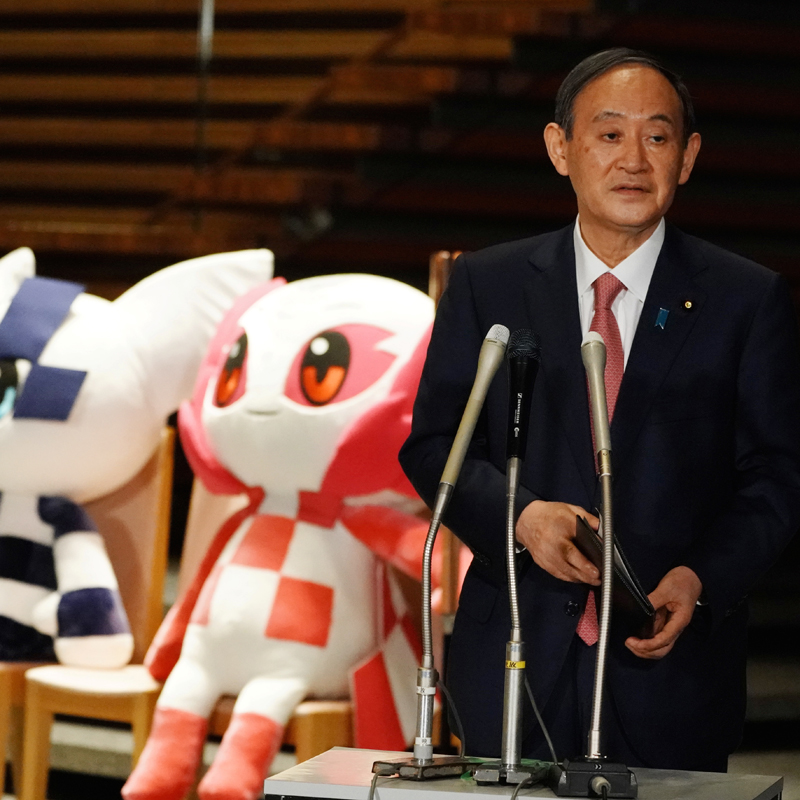「直観」でものごとを判断するということ【中野剛志×適菜収】
中野剛志×適菜収 〈続〉特別対談第3回
「これは普通の事態ではないかもしれない」「彼はちょっとやばいかもしれない」……。最初の直観が、後から考えれば正しかったという経験はないだろうか。われわれは新型コロナについて、どのような第一印象を持ち、どのような発言を行なってきたのか。目の前にある危機は、人々をどう動かしたのか。『小林秀雄の政治学』(文春新書)を著した評論家・中野剛志氏と、『コロナと無責任な人たち』(祥伝社新書)を著した作家・適菜収氏が、小林秀雄とマイケル・ポランニーを題材に、「直観と知の本質」について語る。

■マイケル・ポランニーの「暗黙知」
適菜:前回の対談で「人を説得することは可能なのか?」という問題を扱いましたが、今回はその核心部分をハンガリー出身の物理化学者・科学哲学者のマイケル・ポランニーと絡めて中野さんと論じたいと思っています。
中野:私がポランニーの「暗黙知」で面白いなと思ったのは、ポランニーがプラトンの『メノン』を引いてくるところがある。そこになんて書いてあるかというと、プラトンいわく「問題の解決策を探すというのはパラドックスである」。その意味は、「何を探しているのかを分かっているんだったら、問題はそもそもないじゃないか」「逆に、何を探しているのか分かっていないんだったら、何か見つけられるわけないじゃないか」と。裏を返すと、「「問題は、〇〇だ」といって、問題を設定できるということは、もう答えがどこかにあることを半分知っているからこそできるのである。もし、答えがどこかにあることすら全く分かっていないんだったら、そもそも何が問題であるかも分からないんじゃないか」。そういう面白いことをプラトンが『メノン』の中で書いているのだそうです。
このパラドクスをポランニーは面白がっています。このパラドクスをポランニーは、こう解いてみせた。世の中には言葉とか数字とかで表現できる「明示的な知識」、いわゆる「理論」があるが、それはいわゆる知識と呼ばれるもののごく一部に過ぎない。本当はそういう言葉、数字では表現できないような、「言うことはできないが、知っている」ことがある。それをポランニーは「暗黙知」と呼んだ。「暗黙知」とは、要するに、経験や行為によって、いつの間にか体得しているような知識のことですね。

適菜:ポランニーは「私たちは言葉にできることより多くのことを知ることができる」と言いました。たとえばわれわれは知人の顔とその他大勢の顔を一瞬で区別する能力を持っている。しかし、どのようにして顔を見分けているのかは言葉に置き換えることができない。このように意識の表面には上らないが「知る」という作用に背後で決定的な影響を及ぼしているのが「暗黙知」です。この対談でも述べてきましたが、人間は、知っていることですら、言葉に置き換えることはできないし、意識の表面にも上がってこないのです。
中野:この「暗黙知」によって、プラトンのパラドクスは解けます。つまり、「問題を設定できるのは、答えがどこかにあるのを知っていることだ」というのは、明示的には答えは言えないが、暗黙には知ってる状態です。そして、「問題を解く」「答えを見つける」とは「暗黙に知っていた答えを、明示化することができた」ということなのです。元々、答えの半分は知っていたという状態が、問題の設定。残りの半分を明示化して見つけるのが、答えを出すこと。これだったらプラトンの『メノン』で出てきたパラドクスが解ける、と。

適菜:なにかを予知するということは、後から考えれば、すでに答えを知っていたということになるわけですね。
中野:事実、そういうことは科学の歴史上もある。例えば、コペルニクス主義者たちは、地動説が明示的に証明されていないのに正しいと信じ続けていて、ニュートンが証明するまでの140年間、地動説を信じ続けていた。コペルニクス主義者は暗黙知として地動説の正しさを知っており、それを明示的に証明したのがニュートンだということなんでしょう。
この話は、プラトンだけではなく、あるいはポランニーだけではなくて、いろいろ読んでいると出てきますね。例えば、『保守とは何だろうか』という本で紹介しましたが、19世紀初頭の文人で保守主義者の一人であるサミュエル・テイラー・コールリッジも同じようなことを言っていました。コールリッジが言うには、問題を解決したときというのは、忘れていた名前を思いだそうと努力をした後に似た感覚を伴う、と。問題を解こうとするときは、「なんだったっけ? ほら、あれ、あれ」というような感じになる。そして、実際、問題を解くことに成功すると、答えを忘れていただけで本当は最初から分かっていたような、忘れていたことを思い出したような感じになるというのです。この話は、実に面白い。
適菜:無意識に答えを予知していたから、「やっぱりそうだったな」という感覚になる。私もその『メノン』とニュートンのくだりには感動したので傍線を引いて読みました。大事なところなので、少し長い文章ですが引用しておきます。
《どうやら、ある発言が真実だと認識するということは、言葉として口にできる以上のことを認識することらしい。しかもその認識による発見が問題を解決したなら、その発見それ自体もまた範囲の定かならぬ予知を伴っていたことになるのだろう。(中略)こうした知られざることがらについては明示的な認識など存在しないので、科学的真理を明示的に正当化することは不可能だと言うこともできよう。しかし、私たちは問題を認識することはできるし、その問題がそれ自身の背後に潜んでいる何かを指し示しているのを確実に感じ取ることもできる。したがって、科学的発見に潜む含意(インプリケイション)を感知することもできるし、その含意の正しさが証明されると確信も持てるのである。どうしてそんな確信が持てるのかと言えば、その発見についてじっくり検討を重ねているとき、私たちは問題それ自体だけを見ているのではないからだ。そのとき私たちは、それに加えてもっと重要なもの、問題が徴候として示しているある実在(リアリティ)への手掛かりとして、問題を見つめているのだ。そもそも発見が追求され始めるのも、こうした観点からなのである。すなわち、私たちは初めからずっと、手掛かりが指示している「隠れた実在」が存在するのを感知して、その感覚に導かれているのだ》(『暗黙知の次元』)
このようにポランニーは述べた後で、暗黙知のメカニズムの論点をまとめます。(1)問題を妥当に認識する。(2)その解決へと迫りつつあることを感知する自らの感覚に依拠して、科学者が問題を追求する。(3)最後に到達される発見について、いまだ定かならぬ暗示=含意を妥当に予期する。この種の認識方法によって、問題や虫の知らせといった、途方もなく曖昧なものが認識可能になり、「メノンのパラドックス」は解決されることになると。