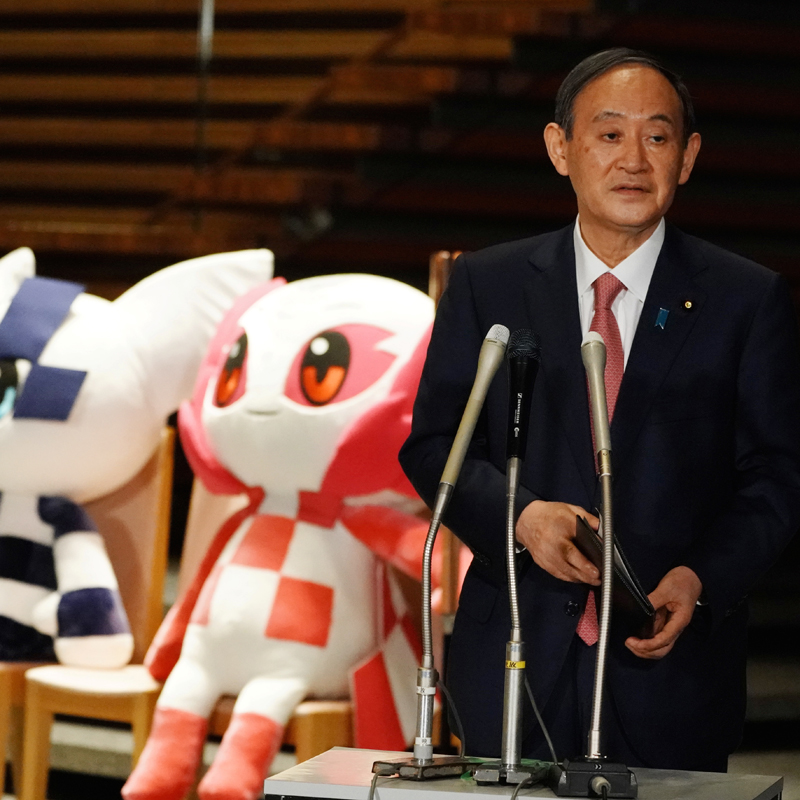「直観」でものごとを判断するということ【中野剛志×適菜収】
中野剛志×適菜収 〈続〉特別対談第3回

■「姿は似せ難く、意は似せ易し」
中野:関連して言うと、ポランニーの科学哲学は、教育とも関係する。例えば、大学があったり、学会があったりしますね。それも国際的にあるわけです。高等教育は昔から、まずは指導教授の下で実験の方法とか、探究の方法とか、議論の仕方とかを訓練する。要するに徒弟制みたいな形で体得していって、それで一丁前になったら、理論を生み出せるようになる。実験の方法とか問題の見つけ方とか論証の手順といったものの背後にも、暗黙知があるのです。その暗黙知を言葉ではなかなか伝えられないので、大学や学会といった科学者の共同体がある。その科学者の共同体の中に住んで、そこで指導教授や他の優れた研究者たちとの交流を通じて、科学の暗黙知を体得していくのです。
もし、暗黙知というのがないんだったら、理論書だけ読んでいればいいわけです。それがなぜ大学の研究室という、ある種の徒弟制があるかというと、科学の暗黙知を伝えるためです。徒弟的な制度でないと、暗黙知を伝えることが難しいからです。世界の科学者たちと交流したり意見交換をしたり、教授たちの議論を見ているうちに、学生の中に、科学の暗黙知が蓄積されていく。だから、科学には、科学者の「共同体」が必要になるのです。科学の暗黙知を伝達し、蓄積するためには、共同体というものが必要になるからです。
科学の世界でよく起きるんですけれども、お互いに交流していないはずの複数の研究者が、ほぼ同時期に同じ発見をすることがある。発明でもそうかもしれない。例えば、電話はベルとエジソンとグレイの3人がほぼ同時期に発明したそうですね。どうしてそういう不思議な現象が起きるかというと、実は、彼らは、科学者・技術者たちが交流を重ねる共同体の中にいて、暗黙知の共有をしていたからだとしか考えられない。
適菜:無意識の部分で共有されていたものが、何かをきっかけに表面化するという。それは問題が共有された時点で、同時に何人かが正確な答えを予知していたということなのでしょうね。
中野:暗黙知は、はっきり理解できないものだから、知るというよりは、理解しないままとりあえず体得する必要がある。つまり、指導教授の教え方とか指導教授の言っていることを、いったんは「信じる」必要があるわけです。もちろんあとになって批判的になっても全く構わないんだけども、学生が未熟である以上、まずは指導教授を信じなかったら指導を受けることになりませんから。まずは信じることから始めないと、暗黙知は伝わらない。だから知る前に信じる必要があるというわけです。「知る」ことの前に、必ず「信じる」ということがどうしても先行するんですよ。
適菜:内田樹が言っていたのですが、師弟関係があるとしたら師なんて誰でもいいと。「弟子が師を信じる」こと自体に師弟関係の意味がある。内田は師から何を学ぶかは二次的な重要性しかないと言います。対象が「情報」に過ぎないのなら、「情報」を学んでしまえば、師は用済みになる。しかし、これでは知的なブレイクスルーは発生しない。理不尽に見える修業の意味は、明示的ではないものを含め全世界に対し、オープンマインドであれということだと。
中野:ただ、残念ながら、信じてはいけない教授、指導を受けてはいけない教授もいることが、このコロナ禍で明らかになってしまいました。あれだけデタラメな言論を展開していれば、研究室の学生にもデタラメを教えているに決まっている。
適菜:また、そこに戻りますか。
中野:どうしてもそこに戻ってしまう。(笑)
適菜:この対談では素読の効果についても語ってきましたが、「論語の意味とはなにか」と小林は問いかけます。
《素読教育を復活させることは出来ない。そんなことはわかりきったことだが、それが実際、どのような意味と実効とを持っていたかを考えてみるべきだと思うのです。それを昔は、暗記強制教育だったと、簡単に考えるのは、悪い合理主義ですね。『論語』を簡単に暗記してしまう。暗記するだけで意味がわからなければ、無意味なことだというが、それでは『論語』の意味とはなんでしょう。それは人により年齢により、さまざまな意味にとれるものでしょう。一生かかったってわからない意味さえ含んでいるかもしれない。それなら意味を教えることは、実に曖昧な教育だとわかるでしょう。
丸暗記させる教育だけが、はっきりした教育です。そんなことを言うと、逆説を弄すると取るかもしれないが、私はここに今の教育法が一番忘れている真実があると思っているのです。『論語』はまずなにを措いても、万葉の歌と同じように意味を孕んだ「すがた」なのです。古典はみんな動かせない「すがた」です。その「すがた」に親しませるという大事なことを素読教育が果たしたと考えればよい。
「すがた」には親しませるということが出来るだけで、「すがた」を理解させることは出来ない。とすれば、「すがた」教育の方法は、素読的方法以外には理論上ないはずなのです。実際問題としての方法が困難となったとしても、原理的にはこの方法の線からはずれることは出来ないはずなんです》(「人間の建設」)。「姿」に「馴染む」という形になる知のあり方があるということです。
中野:同じことを、小林が本居宣長の言葉を引用しているので言えば、「姿は似せ難く、意は似せ易し」ということですね。これは「姿」というのを暗黙知と考え、「意」を明示化された理論と考えるとわかりやすい。理論は伝達しやすいけれども、暗黙知というのは、例えば優れた指導教授の持っている体験ですよね。学問を真剣にやってきた人間だけが持っている体験、こういったものは経験の浅い学生では簡単には真似できないんですよ。指導教授が言っている理論の意味をもっともらしく言うことはできる。でも、そこには、指導教授がその理論を導き出した深い経験は含まれていないから、理論を言うだけでは、本物の科学者になっていない。学生は、指導教授に従って、議論の進め方とか実験の仕方とか、科学者としての立ち振る舞いを体得していく中で、科学の暗黙知を体得し、一人前の科学者になっていく。その科学者としての立ち振る舞いが「姿」ですね。指導教授の「姿」を真似しないと科学者として一人前にはなれないのですが、それは理論を口真似するのとは違って、簡単にはできないというわけです。
適菜:小林はフォームとか型とか形とか息づかいを重視します。言葉ではないもので知が伝達されているのなら、現代人の「さかしら」な解釈ではなくて、対象の「形」「姿」が見えてくるまで見るということです。小林はこう言っています。
《宣長は言葉の性質について深く考えを廻らした学者だったから、言葉の問題につき、無反省に尤もらしい説をなす者に腹を立てた。そんなことを豪そうに言うのなら、本当の事を言ってやろう、言葉こそ第一なのだ、意は二の次である、と》(「言葉」) 。ここでいう「言葉」とは「姿」「形」のことです。宣長はまずは「字」を眺めたのです。素行は「耳を信じて目を信ぜず」と言いましたが、小林はこれを古典の訓詁注釈を信じるな、古典という歴史事実に注目せよという意味だと言います。耳を信じるとは努力をしないでも聞こえてくる知識のことであり、目を信じるとは、眼前に見える事物を信じるのではなく、「心の眼を持て」ということだと。「眼光紙背」という言葉があります。背後にあるものを見抜くという意味です。表面的な「意」だけを重視し、「姿」を軽視する世の中を小林は批判したのです。
(続く)