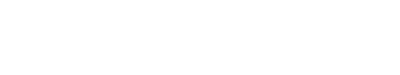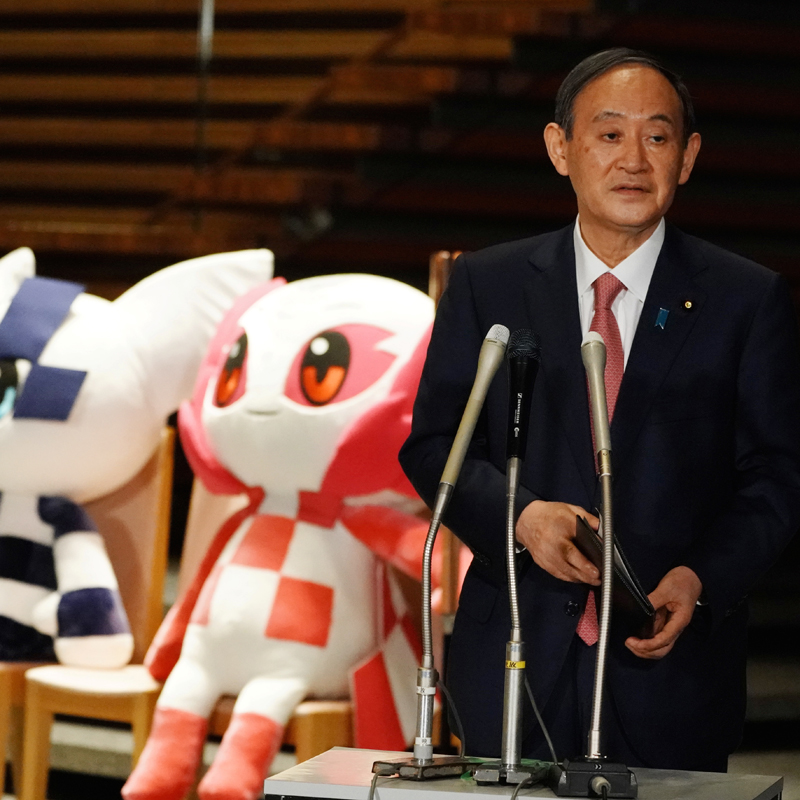コロナ禍は「歴史を学ぶ」チャンスでもある【中野剛志×適菜収】
中野剛志×適菜収 〈続〉特別対談第4回

適菜:柳田國男の学問も一代限りだと小林は言っていますね。柳田は一四歳のとき、茨城県の布川にある長兄の家に一人で預けられていた。隣りには旧家があり、そこにはたくさんの蔵書があった。柳田は身体が悪くて学校に行けなかったので、毎日そこで本ばかり読んでいた。その旧家の庭に石でつくった小さな祠があった。そこには死んだおばあさんが祀られているという。柳田は祠の中が見たくなった。そして、ある日、思い切って石の扉を開けてしまう。
中野:すると中には蝋石(ろうせき)が入ってた。
適菜:そうです。そのとき 柳田は実に美しい珠を見たと思った瞬間、奇妙な感じに襲われ、そこに座り込んでしまい、ふと空を見上げた。よく晴れた春の空で、真っ青な空に数十の星がきらめくのが見えた。昼間に星が見えるはずがないことは知っていた。けれども、その奇妙な昂奮はどうしてもとれない。そのとき、鵯(ひよどり)が空を飛んでいて……。
中野:そう。鵯がピイッと鳴いた。
適菜:それを聞いて柳田は我に帰った。そして、 もしも、鵯が鳴かなかったら、自分は発狂していただろうと柳田はいうわけです。小林はこうした柳田の感受性が、彼の学問のうちで大きな役割を果たしていたと言うのです。柳田の弟子たちは、彼の学問の実証的方法は受け継いだが、感受性まで引き継ぐわけにはいかなかった。だから、小林は「柳田の学問には、柳田の死によって共に死ななければならないものがあった」と感じたのです。
中野:そういった意味では、学問は、なんとか学派とか、なんとか主義とか言うけれども、本当の学問にはそんなものはあり得ない。マルクス主義はなくて、マルクス一代限りとか、みんな一代限り。前回の対談で、指導教授の下で徒弟制みたいに学ぶ話をしたけれども、結局、学んだところで指導教授と同じものを継ぐのではなくて、違うものができる。弟子は、弟子のキャラクターと密接不可分な自分の理論を生み出す。そういう話も、小林が面白がっています。例えば、直接の弟子ではないにせよ影響を受けたという意味では、仁斎と徂徠。徂徠は仁斎と直接接してはいないけど、師として仁斎に学んで、仁斎を越えた。仁斎の古学を学びながら、徂徠独特の学問である徂徠学を作っちゃった。しかし、蘐園学派、徂徠の弟子たちの学派は、徂徠学ではなかった。
あるいは、賀茂真淵と本居宣長。お互い批判し合いながらも、どこか認め合っているような師弟。真淵のことを宣長は心から尊敬していたけれども、宣長は宣長、真淵は真淵というところが残ってしまい、突き詰めると、どうしても折り合えないものがあって、それぞれ真淵学、宣長学になっていく。非常に美しい話です。
適菜:「意」を受け継ぐことはできても、体質は受け継ぐことはできない。しかし、身の振る舞い方、立ち居振る舞いは真似することができる。それが師弟関係ということですね。仁斎と徂徠、真淵と宣長の話もそうだと思います。
■学問や思想が腐りやすい理由
中野:前々回の対談で、小林は若い頃は必死になって批判したり論争したり、説得したりしたけれども、途中から諦めてしまったという話がありましたね。自分の体験とか生来の気質みたいなものが学問や思想と密接不可分になっている以上は、それが言葉による説得によって伝わると考えること自体が、もはや傲慢と言っていい。
適菜:だから「小林に学ぶ」ということは、小林の姿や立ち居振る舞いを見るということになりますね。
中野:姿を見た上で、それを徹底的に真似てみるが、出来たものは、小林とは違うものになる。小林を信じて、小林と違うものを作っちゃう。小林と同じような暗黙知を持っていない、経験を持っていない人間には、小林の言いたいことの想像はできない。だから、若い時分に小林秀雄を読んでも分からないのは、人生経験が不足しているからですね。でも、年を重ねて、いい経験を積んでから読むと、小林秀雄は難しくないことが分かるのですよ。
しかし、もともと、小林と同じような気質がなければ小林の思想は全く理解できない。仮に理解したとしても、小林の言っていることを再現する過程で自分の本来の気質が入ってくるので、出てくる小林秀雄像は、小林自身が考えていることとは完全には一致しない。小林を解釈した結果、言わば、小林と自分が重なったものが出てくるわけです。
適菜:凡百の「小林秀雄論」について、小林自身はこう言っています。《わかったつもりで書いているんだろうが、おれのことをほんとにわかって書いた人は一人もいないね、結局は創作だよ、その人の》(高見沢潤子『兄 小林秀雄との対話』)
中野:もし小林と語り合えたなら、「お前とは、そこは違う」と言って延々二人で論争することになるけれども、経験や気質が近ければ、そして一流の人間同士ならば、意見の一致はみなくても、お互い、相手には敬意を表することにはなる。これが学問の面白さ、楽しさで、こういうふうなことが面白いから、孔子や仁斎の周りにも、弟子が集まってきたのでしょう。「朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや」というわけです。そういう学問の交わりとは、なんとかクライテリオンとかいう雑誌のように、徒党を組むということとは違うんですよ。
適菜:ネット上で「失言者クライテリオン」という言葉を見かけました。
中野:世話になった故人のことをあまり悪くは言いたくないけれども、雑誌『表現者』を主宰した西部邁先生が間違えたのは、そこじゃないかと思う。結局、彼の気質は運動家だったので、徒党を組んだんですよ。徒党を組んで、思想運動をしようとしていたんです。しかし、小林秀雄は、思想はあくまで個人のもので、徒党の思想運動を嫌っていました。この年になってつくづく思うのですが、私は、小林の方が正しいと思いますよ。
適菜:福田恆存も指摘していますが、保守は性格上、徒党を組むようなものではないんですよね。
中野:そうです。『表現者クライテリオン』はその徒党の性格をもっと露骨な形で引き継いでいるように見えますね。西部邁先生の『表現者』も確かに思想運動ではありましたが、個別の問題に関する意見は違っても、それなりの言論人だったら登場させるようなところがありました。ところが、藤井氏の『表現者クライテリオン』には、個別の問題に関して意見が同じだったら、どんな低劣な言論人でも登場する。藤井氏は、消費税反対の徒党を組むため、あるいは緊急事態宣言反対の徒党を組むためだったら、誰とでも手を組み、利用しようとするのです。思想運動を「徒党」と言い、「朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや」を学問の「社交」と言うなら、徒党と社交は、全くの別物です。徒党を組みたがる連中は、社交を知らないガキですね(笑)。この徒党の問題は、『小林秀雄の政治学』で書きましたが、小林が繰り返し論じた「政治」と「文学」あるいは「思想」の区分の問題に深く関わってきます。
あの本で書いたとおり、小林は「政治は虫が好かない」とは言いましたが、政治を否定したり、眼を背けたりしていたわけではありませんでした。政治は集団にかかわるものであり、人間は集団行動をとらずには生活できないことを、小林は重々承知していた。だから、政治は、生活の管理技術に徹すべきだと小林は主張しました。
しかし、思想や文学は、これまで二人で論じてきたように、各個人、もっと厳密に言えば、個人とその周囲の環境、あるいは一言で言えば、その人の「生」といったものと密接不可分なものです。ですから、思想や文学は、個人に固有のものであって、集団のものではない。つまり、政治とは別の領域に属する営みなのです。
ところが、集団を動かそうとする思想がある。本来、個人のものであるべき思想が、集団という政治の領域にからむ。思想が政治化する、あるいは思想が政治に汚染されると言ってもいい。そういう集団を動員しようという政治化された思想が「イデオロギー」です。小林が忌み嫌ったのは、このイデオロギーでした。
適菜:ル・ボンは《群集はいわば、智慧ではなく凡庸さを積みかさねるのだ》と言いました。これは愚かな人間が集まっても意味がないということではなくて、相当なインテリでもつるんでいるうちにバカになるということです。群集の中では個人を抑制する責任観念が消滅し、野蛮で凶悪な破壊本能が出現する。昔、ちょっと調べたのですが、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)、カリフォルニア大学バークレー校、カーネギーメロン大学の合同研究チームが脳のMRIスキャンにより「人は集団で行動すると道徳観が薄れ、倫理的思考ができなくなる」ことを裏付ける脳の働きを発見したそうです。
中野:ですから、小林に言わせれば、思想運動などというものは、邪道ということになる。思想は個人のもの、運動は集団のものだからです。徒党を組んで思想運動をやろうとすると、思想は汚染されてイデオロギーに堕するのですよ。イデオロギーは、徒党・集団が形成できれば、つまり群れができれば成功ですが、群れていては、福沢諭吉が目指した「私立」など不可能です。
だとすると、思想運動をやろうという雑誌は、「思想」ではなく「イデオロギー」の雑誌だということになります。そもそも、「思想運動」などという言葉が形容矛盾なのですよ。運動する群れの中になんか、本当の人間の思想はないのですから。
適菜:本当にその通りです。保守を自称しておきながら「国民運動」を始めると言い出す集団もありましたが、頭が悪いにも程がある。