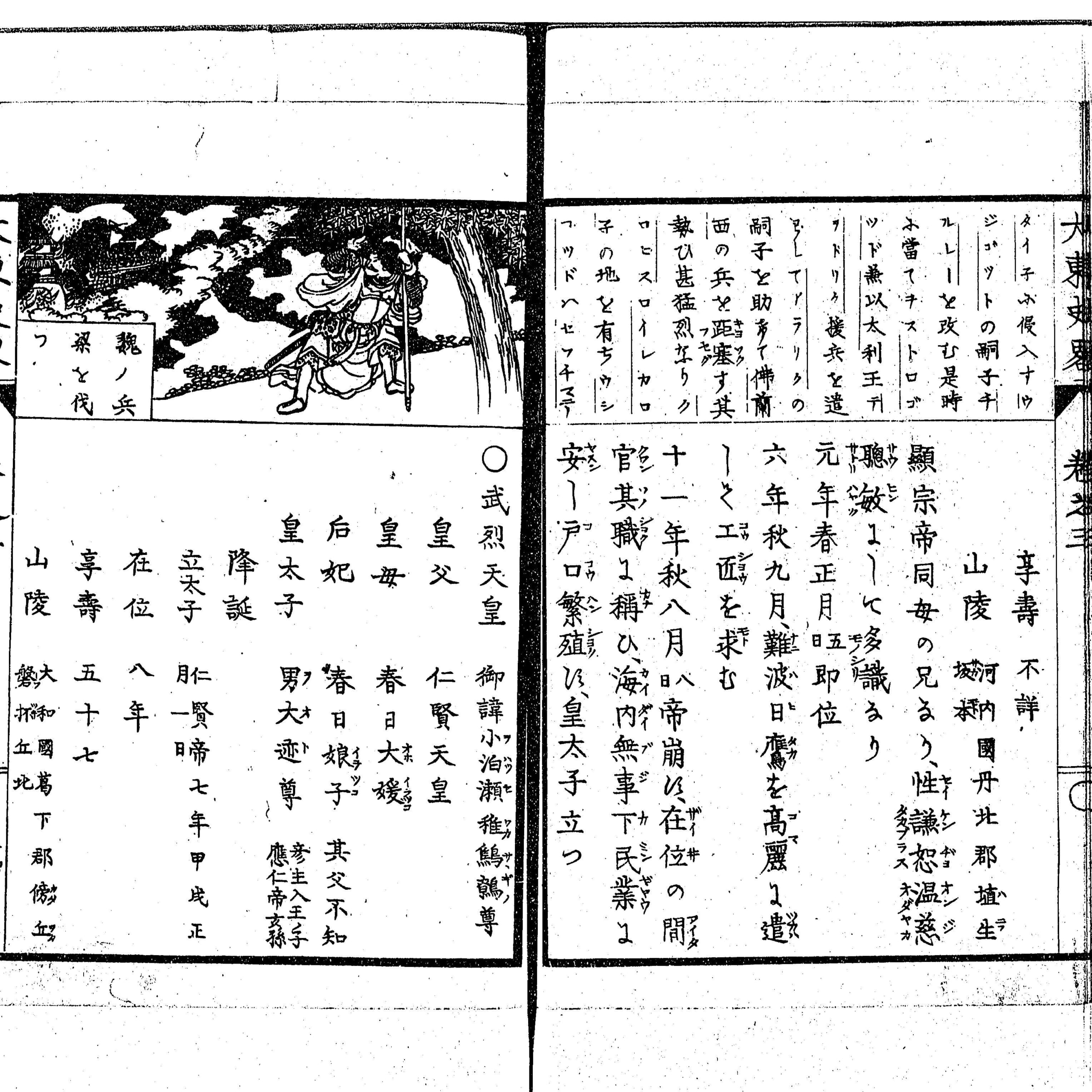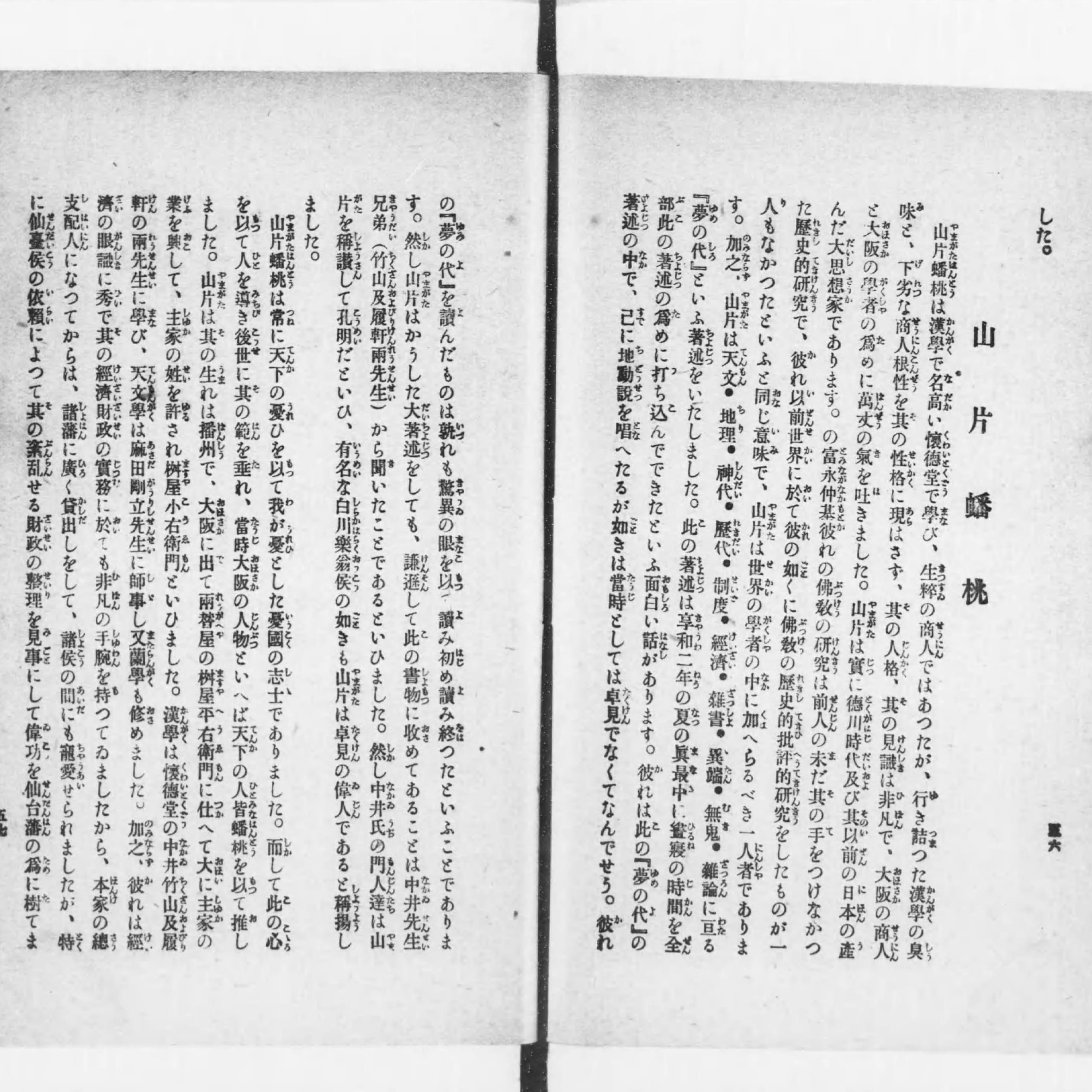"蘇我王朝"成立だった推古天皇、聖徳太子のライン
聖徳太子の死にまつわる謎⑬
■蘇我稲目が継体天皇の外戚となり豪族トップに

継体天皇の誕生は、ひとつの時代の終焉をもたらすとともに、新たな勢力を勃興させることになる。渡来人技術者を配下にしたがえた蘇我氏が、旧豪族を出し抜いて、いちやく政界の中枢に躍り出たのである。
当然のことながら、ここに新旧勢力の軋轢が生じた。そして蘇我氏は一族の女を天皇に嫁がせ、天皇家の外戚という立場を利用して次第に他の勢力を圧倒していく。
こうして、馬子・蝦夷・入鹿という三代が、蘇我氏の全盛期を築きあげることになる。彼らは、天皇といえども自分たちのいうことを聞かなければ即座に排斥し、傀儡としての天皇を擁立、権勢をほしいままにしていた。
このような情勢のなかで、蘇我氏はこれ以上の布陣はないといえるほどの強固な体制を敷いた。つまり、蘇我系の皇族・推古(父が欽明天皇、母は蘇我稲目(いなめ)の女・堅塩媛(きたしひめ))を天皇に、そして蘇我系の聖徳太子(父は推古天皇の兄・用明天皇、母は蘇我稲目の孫・穴(あな)穂部間人(ほべのはしひとの)皇女(ひめみこ)、妻は蘇我馬子の女・刀自古郎女(とじこのいらつめ))を皇太子に据え、さらに馬子自身が大臣として実務を動かすといった、まさに“蘇我王朝が誕生したのである。 馬子はこうして実質的に朝廷を支配したが、そんな馬子にとって聖徳太子という存在は、あくまで大王家を私物化するための道具にすぎなかった。だからこそ太子を庇護し、摂政という形で実質的な政治運営を任せたのである。
ところが、思わぬところに落とし穴があった。
蘇我氏の影響を強くうけた聖徳太子ではあったが、ひとたび摂政として大王家を代表する立場になってみると、馬子の要求と大王家の利益を守る役目の板ばさみとなり、次第に両者は不協和音をかもしだすようになっていった。
それはやがて明確な敵対関係となって、朝廷内に亀裂を生じさせることになる。
たとえば推古16年(608)、隋との国交樹立という一大国家プロジェクトに、 馬子を筆頭とする蘇我一族がまったく姿を現さなかったことは、両者の確執が表面化したことを象徴しているといわれている。また、これとは対照的に、推古18年 (610)の新羅使来日に際し、蘇我馬子・蝦夷親子のみがこれに関与し、大王家はまるで無視するかのように姿を現さないことも同様である。
〈『聖徳太子は誰に殺された?』〉より