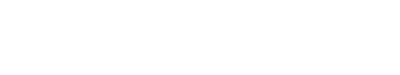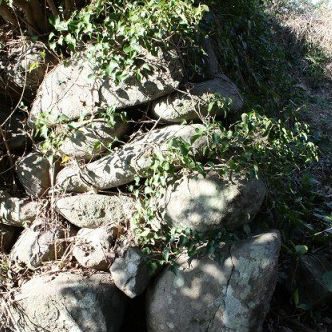津軽家VS南部家 仁義なき?築城合戦
外川淳の「城の搦め手」第77回
『歴史人』では武将の「ライバル関係」についての特集をこれまで何度かしてきた。私も津軽為信と南部信直の対決などを分析したが、「BESTT!MES」を利用し、為信が南部への対抗意識から築いた弘前城について考察を加えてみたい。

津軽為信銅像
戦国武将の銅像のなかでは極めて高いクオリティを誇る。
戦国武将の銅像のなかでは極めて高いクオリティを誇る。
津軽家は南部家に負けない城を築くことにより、自身の力を誇示しようとした。
対する南部家も同じように巨大かつ堅固な城を築くことにより、津軽家よりも優位であることの証明としようとした。
津軽家は、為信の代に大浦城から堀越城に本拠を移していた。為信の死後、津軽家を相続した信枚は、高岡城(のちに弘前城と改名)の造営工事に着手。
同じころ、南部家は盛岡城の造営を開始しており、直接対決ができない両者は、築城合戦によって優劣を競ったともいえよう。

弘前城天守
欄干前に写り込むのは、電動アシスト付折り畳みの愛車。弘前は取材のため自家用車で往復。城内の探査には4輪車に搭載した2輪車で巡る。
欄干前に写り込むのは、電動アシスト付折り畳みの愛車。弘前は取材のため自家用車で往復。城内の探査には4輪車に搭載した2輪車で巡る。
弘前城は、天守下の石垣の「はらみ」により、積み直し作業が決定。天守が曳家によって移動される大工事となり、今も作業中である。詳しくはHPをチェック。
城の中心に位置する天守を比較すると、弘前城は五層の天守が聳えていたのに対し、盛岡城は三層の櫓を天守の代用とした。
つまり、建物という面では、4万7000石の津軽家が10万石の南部家を上回っていた。
二つの城を比較すると、素人目には建物が林立する弘前城を優勢と判断しがちではある。
だが、総石垣といえる盛岡城の守りは強烈であり、こちらの方が玄人受けする堅城だといえよう。