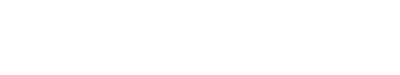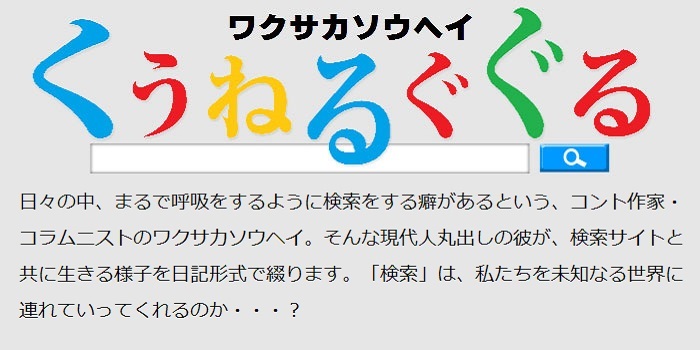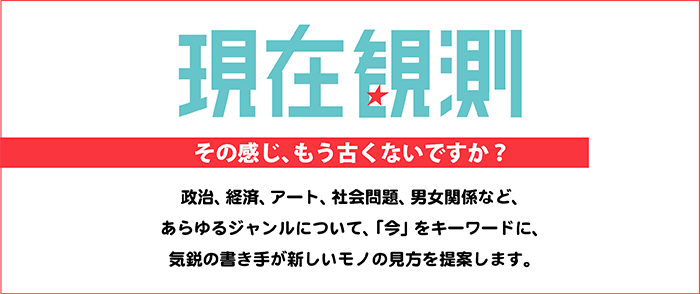Scene.4 気分はいつもライブ。
高円寺文庫センター物語④
「こんにちは、相変わらず賑やかでいいですね」
「あは、大原さん。いらっしゃいませ」
「いやね、以前、店長が読んでいるって話していた『ちくま文学の森』買わせて戴いたじゃない」
「はいはい、シリーズの『14巻・ことばの探偵』でしたよね?」
「読み耽ってしまってね。今度は『3巻・幼かりし日々』をお願いしようかと思って来たの」
「嬉しいなぁ、お気に召しましたか?!」
「もちろん。店長が言うように、どうしても自分の好きな作家ばかり読んでしまうでしょ。他の作家に手を伸ばすのは躊躇してしまうけど、アンソロジーだと抵抗なしにアプリオリに世界が広がっていくのよね。」
「でしょ! 大原さんも、アンソロジーの魅力に取りつかれましたね」
「このシリーズは、気になった巻を読み続けたいんだけど。
店長みたいな読書家の読んでいる本を聞いてみたくて、自分の読書計画にスパイスを加えようと思って来たの」
「そしたら知の巨人と言われる荒俣宏かな、立て続けに『帝都物語』『妖怪草紙』『日本妖怪巡礼団』を読んだんですよ。
あとは松下竜一の『小さなさかな屋奮戦記』と、藤森照信の『建築探偵の冒険・東京篇』が印象深くて刺激的だったかなぁ」
「店長はさ、本の感想で面白かったとか使わないのが言葉を考えているよね。松下竜一は『豆腐屋の四季』以来、忘れていたの。文庫になるまで待とうかな」
「ゲゲゲ、営業的には買って戴きたいけど。大原さんの読書量じゃ、毎月の財布がたまらないでしょうね!」
「はは、商人でも正直者はイヤミじゃないね」
「本屋さん、ラブホテルのガイドはないかな?」
う! 一瞬、つまった。
前に勤めていた神保町の本屋「書泉」では、定期的に担当ジャンルの異動があった。そこで、すべてのジャンルを経験しているので本や雑誌の知識には自信がある。
高円寺に移ってからも、業界紙の「新文化」と取次店から送られてくる「日販速報」「日販通信」に、各出版社からの新刊案内や朝日新聞などと最新情報にも怠りなく目を配っていた。
記憶力は減退を始めても、不思議と本のことは脳みそに入ってくる。
しかし、ラブホテルガイドは・・・出てこない。
「すいません、ガイドとしては出ていないはずです。雑誌でたまに、紹介されるくらいなんですよ」
お客さんのご要望に応えられないという、たまらない敗北感。
その手を出していそうな出版社に電話してみても、やはりない! この顛末は、来店する出版社の営業さんたちに話し続けた。
「店長、出ましたよ。これ、コピーです」ある出版社の営業さんが、知らせてくれた。新刊案内を見落としていたのかな?
その『ラブホテルガイド』を出した出版社には「実はね!」と、思わず電話してしまった。