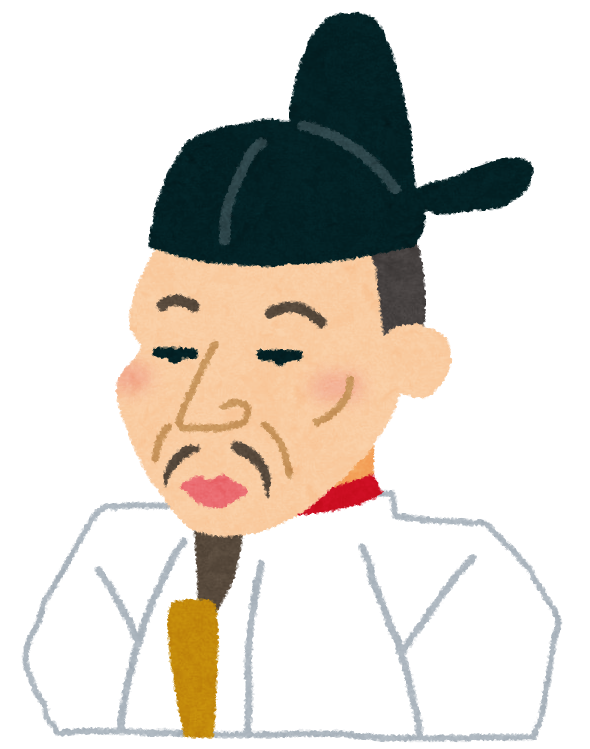「悪人こそ救われる」の本当の意味
煩悩への罪の意識に悩んだ親鸞がたどり着いた答えとは
究極の価値転換を説く『歎異抄』

浄土真宗の宗祖・親鸞(しんらん)は、どきりとするような言葉をいくつも残している。それも本心からのものなのでより心に重く響く。たとえば、『歎異抄(たんにしょう)』の次の一節。
「弥陀(みだ)の五劫思惟(ごこうしゅい)の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり」 (阿弥陀仏は五劫という長い時間〈一説に1劫は43億2千万年〉思惟を重ねて仏になられたとき、念仏を称えた者はすべて極楽浄土に迎えるという本願を立てられたが、これをよくよく考えてみると、ひとえに親鸞一人のためであったと思われる)。
経はすべての者の救済について述べているのに、親鸞は「親鸞一人がため」と言う。どのような心の変遷を経て、この境地に至ったのだろうか。
承安3年(1173)、親鸞は藤原氏の一族である日野家に生まれた。藤原氏の一族とはいえ末流で、あまり豊かではなかったようだ。そのためか親鸞の兄弟はみな仏門に入っている。 親鸞自身は9歳で出家、比叡山に入り常行三昧堂(じょうぎょうざんまいどう)の堂僧となった。常行三昧堂は念仏三昧などの行を行なう堂で、親鸞は日々念仏を称える生活を送ったものと思われる。
だが、当時は寺院間の紛争が絶えず、比叡山内でも僧兵同士が争うという状況で、修行や学問に専念できる雰囲気ではなかった。下級貴族出身の親鸞には僧としての出世も見込めず、その修行生活は鬱々としたものだったろう。
親鸞の神秘体験
転機が訪れたのは29歳のときであった。その年、親鸞は京の六角堂で百日間の参籠を行なった。親鸞の妻・恵信尼(えしんに)の手紙によると、95日目に聖徳太子が現われ、親鸞に文を渡したという。文は現存していないので何が書かれていたか分からないが、女性と交わる罪を犯しそうになったら観音が玉体の女人に変じて妻になり犯されよう、という「女犯偈(にょぼんげ)」が書かれていたのではないかと考える研究者が多い。
この神秘体験ののち、親鸞は法然に弟子入りをし、その庵に百日の間通って他力本願の信仰を固めたという。すぐに弟子の中でも頭角を現わすようになり、4年目にして『選択本願念仏集(せんちゃく《せんじゃく》ほんがんねんぶつしゅう)』の書写を許されている。
おそらくこの時期に「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」の悪人正機の教えも伝授されたのであろう。自分の著書『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』に「悲しきかな愚禿鸞(ぐとくらん)、愛欲の広海に沈没し」と書くほど罪の意識の強かった親鸞にとって、自力では煩悩の世界から抜け出すことができない悪人こそを阿弥陀仏が救いの対象とする教えは、感銘深かっただろう。
しかし、師との時間は長く続かなかった。既成教団からの告発などにより、法然は土佐へ、親鸞は越後へ流罪となったのである。この処分に腹を据えかねた親鸞は、自らを僧でも俗人でもない非僧非俗の愚禿と称し、公然と妻帯生活を送った。 不本意な形で始まった東国の庶民への布教であったが、この間に親鸞は他力本願の信仰を独自に深めていった。
親鸞は愚かな凡夫が往生することは、阿弥陀仏が本願を立てたことにより、すでに決定されたことだと考えた。信仰心すら阿弥陀仏から与えられるものとし、阿弥陀仏が衆生一人ひとりに与えた約束としたのである。「親鸞一人」という言葉はここに拠っている。
さらに親鸞は信心を得た者は誰もが往生が約束された存在として、弥勒菩薩に等しいとした。阿弥陀仏の本願を信じることで、罪深い人間もそれだけの価値が見出せる、と説くのである。