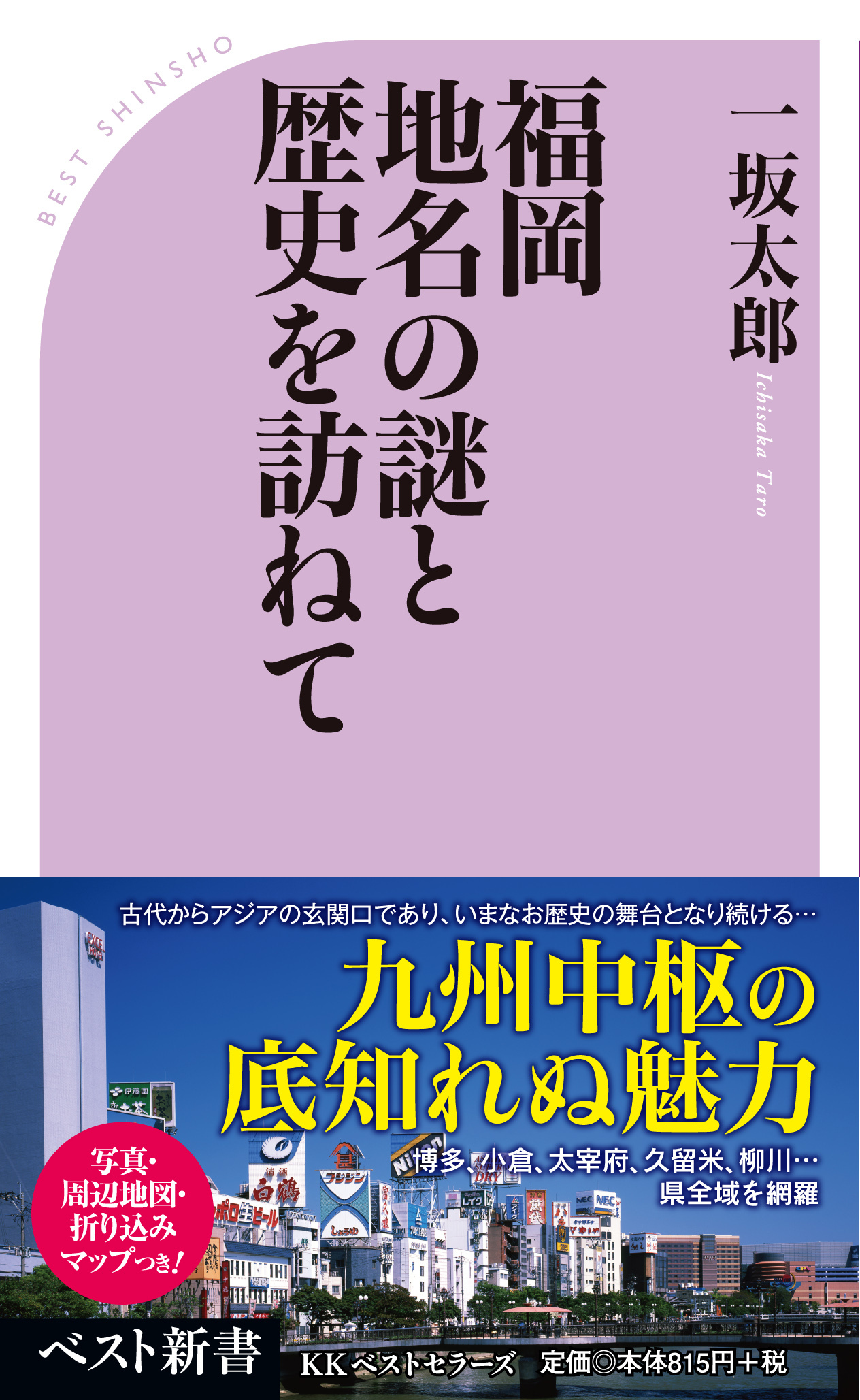「幅広くお仕事をされていますが、“専門性”とはなんですか?」古市憲寿さんに聞く!(3)
一つの世界に閉じた「専門性」には意味がない
複数のフィールドに身を置くということ

僕が自分を「社会学者」だと強く思ってないこととも通じるのですが、あんまり「これだ!」って専門を意識したことはありません。
もちろん「若者が日本でどう論じられてきたか」や「ノルウェーの育児政策」には日本の中でもかなり詳しいほうではあると思います。ただそれを一生かけて突き詰めていくつもりはありません。人生って短いですから。
人にはそれぞれ向き/不向きがあります。僕はひとつの世界に閉じこもっていることが好きじゃありません。むしろ自分ができること、関わった世界をつなげていくほうに価値があると思っています。
その意味で、今はあえて専門家ではない立ち位置から少子高齢化に関して興味がありますね。
僕自身は研究自体は好きですが、大学という場所にこだわりはあまりありません。これから大学の数はどんどん減っていくでしょう。そして文系はもともと大した予算がつくわけでもありません。人が減った分これまでやらなくてよかったような雑務が増える一方で、研究成果はシビアに求められ続ける……大学での仕事だけが生きていくための命綱になってしまったら、こんな大変な環境にしがみついていかなきゃいけない。それは僕には無理。なので、大学の外に働く場所を求めるようにしてきました。
ひとつに絞らない方が、僕にとっては居心地がいい場所になるんです。たとえ1つのフィールドがダメになってしまっても、ほかの居場所が残っている……こう思えることは、精神的にも楽にもなります。
常に複数のフィールドに身を置きながら、新しいフィールドも探し続ける――これって研究者に限らず現代では多くの人が求められる働き方ですよね。
実際、「ここがダメでもほかがある」と思えていた方が、自分の現状を冷静に判断できます。業務上でも意識的に汎用性のある知識や技術を習得して、外にもコミュニティを持つことが、先々のリスクヘッジにつながるはずです。
自分では無理だと思っていることでも、意外と周りから求められたり、評価されたりすることもあるんです。
だって、こんなに滑舌の悪い僕が、依頼を受けて毎週テレビでコメンテーターをやっているんですよ?(笑) 物事の向き/不向きは、自分の認識だけではなく、周りとの関係性から判断する意識を持てると、人の可能性は大きく広がるのかなと思います。