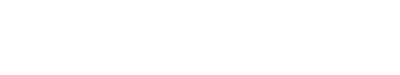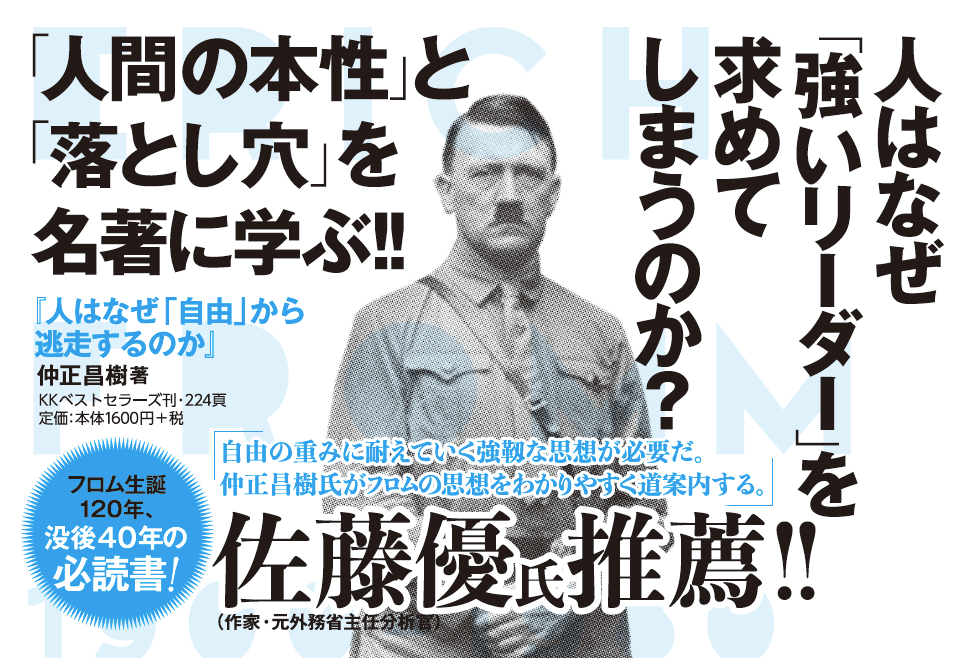統一教会問題で「政教分離」という言葉が独り歩きしている危険な兆候【仲正昌樹】
「政教分離」という言葉を、理解しないままやたらと使いたがるお子様な人たち
安倍元総理暗殺事件のあと、統一教会問題に関する話題が尽きない。これまで私たちが意識せずに見過ごしてきた「政治と宗教」の関係という大きな問題が顕在化した意味は大きい。一方で、そこで語られる「政教分離」という言葉を私たちは理解しないまま使ってはいないだろうか。そこに見られる危険な兆候とは何か。哲学者で金沢大学教授、そして『統一教会と私』という著書もある仲正昌樹氏に緊急寄稿してもらった。

■「政教分離」と「信仰の自由」
安倍元首相銃撃事件の背後にあったとされる、容疑者の統一教会への恨みをめぐる問題がマスコミで大きく取り上げられるようになるにつれ、「宗教と政治」の関係という大きなテーマが浮上してきた。
連日、自民党を始めとする政治家と統一教会の“癒着”が伝えられるたびに、ネットで、「政教分離の原則」に違反している、という声があがる。しかし、“政教分離”を口にしている人の多くは、“政教分離”とは何かをよく分かっておらず、雰囲気でこの言葉を使っているようである。中には、統一教会との何らかの“関係”が明らかになれば、それだけで憲法違反であり、議員辞職に値すると言わんばかりの強引な“意見”もある。
しかし、それは付き合っている相手が“統一教会”だとそれだけで“政教分離”の原則の違反になり、創価学会や幸福の科学など他の宗教団体だと、必ずしもそうでもないということなのか、それとも、これらの団体と付き合いも本当は“政教分離”違反だと言いたいのか。明確な基準もないまま、“政教分離”という言葉が独り歩きしている状態は健全ではない。
私自身と統一教会の関係は、『統一教会と私』(論創社)等で繰り返し説明したので、前回同様、詳細は省き、政治思想史研究者の立場で、「政教分離」と「信仰の自由」とは何か考えてみたい。
政教分離の原則の原点は、宗教改革期以降の西欧における、キリスト教の宗派間の烈しい戦争だ。中世のヨーロッパでは、法王を始めとする高位聖職者は広大な領地を持ち、世俗の政治に様々な形で関与していた。だが宗教改革で、プロテスタントの諸派が分離したことで、カトリック教会の権力基盤は根底から掘り崩され、様々な宗派が争うことになった。
三十年戦争(一六一八-四八)では、カトリックvsプロテスタントの信仰の争いに君主間の権力闘争が結び付き、ヨーロッパ全体を巻き込む激しい戦闘が続き、ドイツの人口の三分の一が失われたとされる。この戦争を終結させるために締結されたウェストファリア条約で、宗教と政治の力関係が大きく変わることになった。条約では、各国を支配する君主の主権者としての地位を認めると共に、それぞれの君主が自国の国教をカトリック、ルター派、カルヴァン派のいずれかで選択できることになった。これを機に、宗教が世俗の政治を支配するのではなく、逆に政治が宗教を統治の対象にするようになったのだ。
次の段階では、次第に中央集権化していく主権国家の課題として、宗派間の争いが政治の不安定化に繋がることをどう抑えるかという問題が浮上した。国家が国教制度に拘り、出産死亡などの届け出を、特定の宗派の教会を通して行うことを義務化したり、非国教徒の財産権や公職への就任を否定し改宗を促したりすると、それを拒む人たちの抵抗が強くなる。フランスや英国では実際、それが長年にわたって大きな内乱をもたらし続けた。
社会契約論によって、国家の目的が広い意味での「所有権」の保障であることを明らかにしたことで知られるロックは、『寛容に関する書簡』(一六八九)で、何が正しい信仰であるかは、政府による統治の管轄外であるという前提に立ち、国教徒と非国教徒を差別的に扱うべきではないと主張した。この著作でのロックの議論は、たとえ自分にとって見るに耐えない信仰であっても、他者の信仰を尊重し共存を目指すべきとする「寛容 tolerance」論のモデルになった。

信仰を個人の問題としてより明確に位置付けたのは、功利主義の哲学者ジョン・スチュアート・ミルだった。今でも自由主義の政治哲学の最高の古典とされる『自由論』(一八五九)で、民主社会における人間の活動領域を、多数決による決定に従うべき「公的領域」と、他者に直接影響を与える可能性が低いため、原則各人の自己決定に委ねるべき「私的領域」に分割した。そのうえで人がどのように生きるべきか説く宗教は、後者に属するはずだと指摘した。
ミルはこれまでの西欧の歴史で、他者がどういう信仰を持っているかに拘ったことがどれだけの対立をもたらしてきたかを繰り返し強調したうえで、どの宗教を信じるかは、各人の生き方の選択の問題であり、それを他人に押し付けようとすることがそもそも間違いなのだ。民主化された国家は、宗教など内面の問題に干渉して対立を煽るのではなく、むしろ社会の中に多様な考え方が存在するよう配慮すべきだ、という。

人々の生き方に対する宗教組織の影響力が弱まり、国民統合の観点から宗教や思想・信条の違いに関係なく人々を平等に扱う必要が高まったことから、近代国家は「政教分離」と「信教の自由」を基本方針とするようになった。しかし、個人に対する権利保障の問題である「信仰の自由」と違って、政治や法律全体の仕組みに関わる「政教分離」については、それをどの程度徹底するかは国によってかなり異なる。
英国は、国王を長とする国教会制度は維持しており、貴族院では国教会の高位聖職者が聖職貴族として議席を持っている。ただ現在は、国王や貴族院の政治的影響力はロックの時代に比べてかなり限定されるようになったので、下院を中心とする内閣制は実質的に政教分離で運営されていると見ることもできるが、厳格なものではない。
アメリカでは一七九一年に成立した憲法修正第一条項で、「連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律」を制定してはならないとしている。しかし周知のように、大統領の宣誓式の際に左手を聖書の上に置くことや、紙幣や硬貨に〈IN GOD WE TRUST〉と印字されているなど、キリスト教が政治文化のベースになっていることを感じさせる表象は少なくない。
公教育についても、フランスのように「世俗性」の原理を徹底し、特定の宗教を連想させる事物を一切持ち込ませないようにしている国もあれば、ドイツのように、憲法に当たる基本法で、宗教団体の教義に従って行われる「宗教教育」を公立学校における正規の授業として認めている国もある。フランスのように、「世俗性」の原理に拘りすぎて、教室でイスラムの少女たちがスカーフを着用することまで禁じると、かえって、少数派の宗教生活が難しくなるよう国家が干渉しているような様相を呈する、という逆説が生じる。