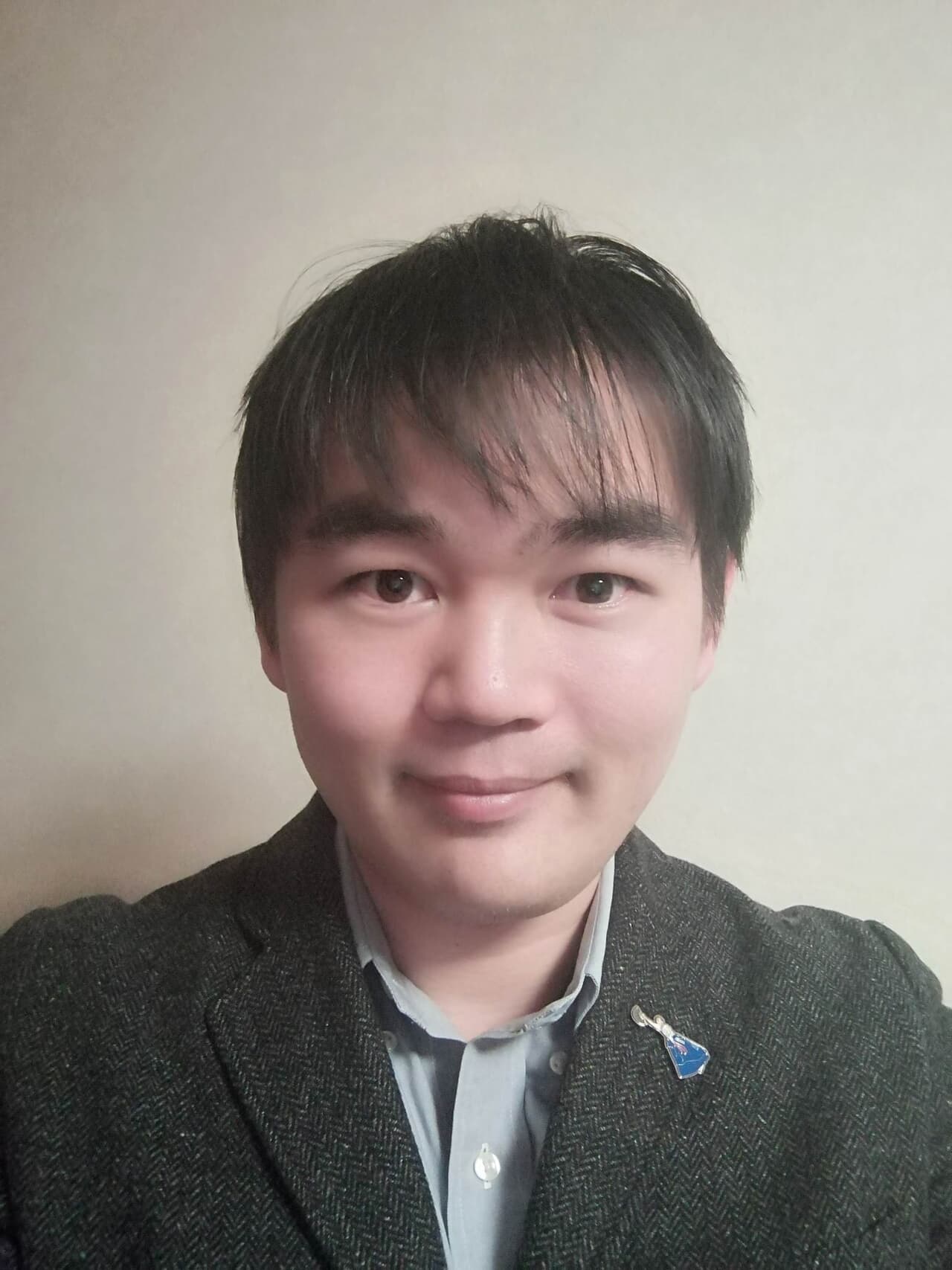【芥川賞候補に!】ブックライターが読んだ 向坂くじら『夫婦間における愛の適温』。そして感じた清々しいまでの嫉妬心【甲斐荘秀生】

◾️「俺は、こんな風には書けない」
詩人・向坂くじらと知り合ったのはたしか5年ほど前のことで、それからは観客として詩の朗読を聞いて感動したり、時には彼女が出演する朗読ライブの裏方スタッフをしたりと、彼女の表現を鑑賞する機会がなんだかんだ年に一度くらいある。10歳ほど年下の友達である彼女のことを、表現者として尊敬してもいる。
よく広告などで「待望の」という表現を目にするが、だから私にとって彼女の初エッセイ集『夫婦間における愛の適温』はまさに「待望の一冊」だった。
本書の発売日、私は近所の焙煎店のテラス席で珈琲豆の焼き上がりを待ちながら、先刻届いた本をワクワクしながら読み始めた。
「なにより気持ちいいのは、頭の中で考えていたことにすらっと一本の線が通るときだ。混沌とした事象が、ぱちぱちっと音を立てるようにつながって、自分の考えがとても自然に、スムースに感じられる。」
(本書収録「俺は論理的に話したいだけなんだけど、彼女はすぐ感情的になって」より引用)
といった、ひとつひとつの言葉があるべき場所に収まった、流れるような文の美しさに、「うわあ、巧いなぁ」と思わず感嘆の声を出しながら、4編のエッセイと、息継ぎのように挟まった1編の詩を読み終えたところで、焼き上がった珈琲豆を店員さんが持ってきたので一旦本を閉じた。
そうして息をついた時、それまで素晴らしい文章を読む愉悦に浸っていた自分が、同時に「俺は、こんな風には書けない」という敗北感を感じてもいることに気がついた。
最初に書いた通り、向坂くじらの作品にはこれまで何回か触れてきた。彼女がギタリストのクマガイユウヤと組んでいる朗読ユニット「Anti-Trench」のパフォーマンスを初めて観た時には、心底感動して、本人に長文のメッセージを送ったりもした。それでも今回のように「敗北感」を感じたりはしなかった。
今になって考えると、私は自分を「詩人ではない」と思っていて、観客という安全な立場から作品を受け取っていたから、無邪気に感動だけできていたのだろう。舞台の下から観ているだけの人間は、舞台の上の人間が発した「言葉」を、真正面からひとりの人間として受け止めたつもりでも、作品の「凄まじさ」に打ちのめされる必要はない。自分自身が作品を創らない以上、「俺にはこの作品は創れない」という単なる事実に打ちのめされる必要はなく、むしろ「自分には創れないから観に来て良かった」と満足する材料になるだけだ。