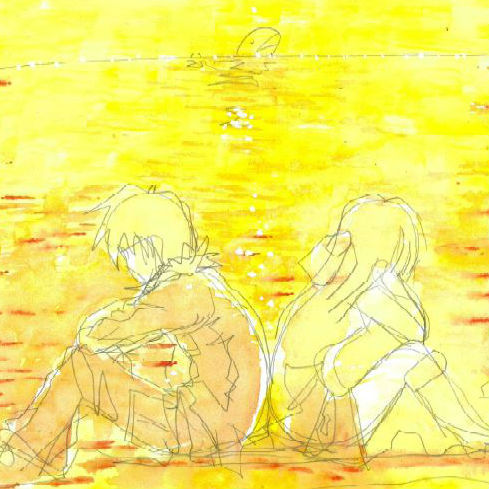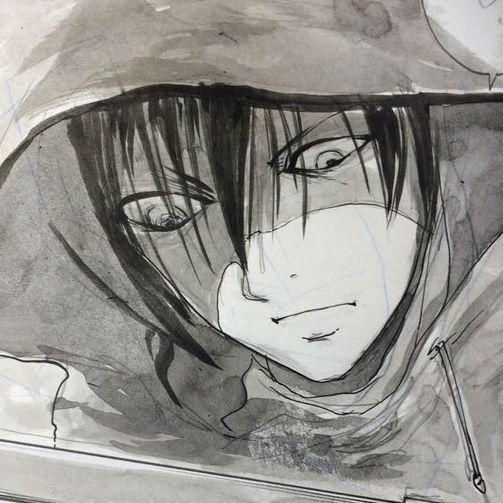ビレッジバンガードの皮肉な現実
「自分だけが特別」と「みんなと変わらないもの」のあいだ
漫画家・山田玲司がその二つの世界観の中に、現代の若者の意識を見出す。
ビレバン的なるものと、タワレコ的なるもの

サブカル趣味の雑貨と共に本なども売るスタイルで人気のビレッジバンガード(通称ビレバン)は、個々の店の店長のセンスで品揃えが決まるという。
興味深いのは「サブカル寄り」と言われているこの店の商品には、何かしら共通の要素があるということだ。それはアバウトに言って「内向的」「個人的」「カルト趣味」「メンヘラ傾向」で、要約すると「自分向けの世界」だ。
そこには「センスのいい私にはわかる特別なセンス」が誇示される空気がある。
思春期の「自分以外はみんなバカ」という排他的な空気で、そこに来るお客さんは「その感じ」を共有しているわけだ。
こういうのは文学好きな若者が通る伝統的な道で、かつては神保町の古本屋街や新宿ゴールデン街などにあった。その「知的でアウトサイダーな気分」は、高円寺、下北沢、秋葉原などに居場所を求めつつ「ビレバン」という形に収まって各地に広がった。
この店の成功の背後には、今の若者の多くに「自分は特別で、他のバカ(一般人)にはセンスがない」という、内向的排他主義が蔓延していたからだろう。
そんなビレバン世界の対極にあるものの一つが、タワーレコード(通称タワレコ)だろう。
集団アイドルから大御所ベテランミュージシャンまで、その時に売れているメジャーな商品を店頭に積み上げて、その基準は「売れている」もしくは「レコード会社が推している新譜」が基本だ。
そこには店長のセンスの余地や、自分だけが知っているいいもの、という理由で選ばれている商品は見当たらない。店舗スペースは貴重で、売れる商品のために使われる。売れない商品は順次店舗から消えていく。
これは書店も同じで、基本的に小売店に商品の選択肢はなく、そのせいでどこの書店に行っても同じような品揃えになっている。こうなると直接店舗を巡ってもたいした発見がないので、必然的に駅に近い大きな書店が有利になってしまう。
そして何より「みんなが買うもの」しか目につかないため、それが自分の趣味に合わないとCDや本そのものから興味が離れてしまう。毎月恐ろしいほどの点数の書籍が発売されているのに、目につくのは一部の大ヒット作だけなのだ。
こうなると、その文化は脆弱で貧相に見え、業界全体が豊かさを失ってしまうのだ。
この「売れるものが店舗の前に」という売り方は、ビレバンにも見られていて、「自分だけがわかる」センスが売りだった店舗に、タワレコ的な「大ヒット大メジャー商品」が並んでいることも増えてきたように見える。
売上げがなければ存続できないので、苦肉の選択なのだろうが、ここには「自分のセンスは特別」といいながら、実は「みんなと変わらないもの」を選んでいる、サブカル趣味を自称する人たちの皮肉な現実も垣間見える。
「みんなの知らない特別なもの」が目的の店ならば、店頭にメジャー商品を並べなくても商売は成立するはずだ。
この2つの種類の小売店を見ているとわかるのが、若者の世界が「自分だけが特別」という意識と「みんながいいなら大丈夫」という世界に分かれていることと、実はその境界も曖昧だということだ。
「自分以外はみんなバカだ」とか「自分だけがわかる世界」に耽溺している時期はあっていい。問題はそこから脱却することは「負け」ではないということだ。
その実、タワレコにもいいコンテンツは存在するし、タワレコに積まれた廉価版の昔のジャズCDなどの中にも伝説の名盤があったりする。タワレコのような「普通の店」に、平然と行けるようになれば、「そういう問題から解放された時代」に入るのだ。
それは、「みんなと同じつまらないヤツ」になるのではなく、「そんなことはもうどうでもいいというステージに入る」ということなのだ。