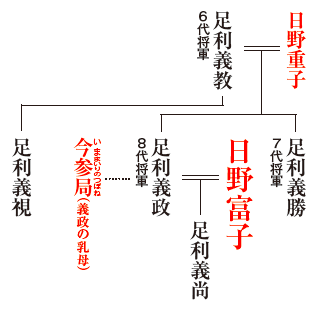海外から絶賛される日本の花火
奥深き日本の花火を改めて見つめる
花火大会はひと夏で、全国約4500大会が開かれている。しかし一方で、知らないことも数多い。
そこでハナビストの冴木一馬さんにその歴史や基本を尋ねた。
そこでハナビストの冴木一馬さんにその歴史や基本を尋ねた。

「花火が多くの見物客を集めるようになったのは江戸時代の末期。隅田川花火大会の起源である両国の川開きを知らせる花火で、『玉屋』や『鍵屋』などの花火師が活躍した頃です。そういった町人による花火文化が各地で伝承され、現在に至っています」。
世界一美しいとされる日本の花火は、どう発展してきたのだろう。
「江戸時代初期の花火は『龍勢(りゅうせい)』と呼ばれる、筒に黒色火薬を詰め、柄を取りつけた単純なものでした。それが花火職人などの研究によって、『ポカ物(*1)』 や『型物(*2)』などに進化しました。その後、日本で生まれた『割物(*3)』と『半割物(*4)』は、実に日本人らしい緻密な設計の花火ですね。複数の色を出す火薬を使った鮮やかさは、海外の花火にはありません。その芸術性が高く評価されているのでしょう」。
シーズン到来直前。これら基礎を学び、ひと味違った視点から花火を堪能してはいかがだろうか。
*1…ポカ物
4つの中で一番古く、上空で2つに割れるときに“ポカッ” という音を発することから命名。「柳」や「蜂」などがある。*2…型物(かたもの)
ポカ物に次いで古く、江戸末期頃に登場。玉の中に色の異なる火薬で形を作ることで、打ち上がった際にその形が現れる。*3…割物(わりもの)
「菊」や「牡丹」などの日本固有の種。割薬と呼ばれる破断薬を詰め、外を星(花弁)という火薬が囲む。これを複数層に重ねたものも。*4…半割物(はんわりもの)
割物とポカ物の特徴を持った花火で、「千輪」や「花雷」などが有名。小さな玉に火薬を詰めた後、5号~四尺の大玉に小玉を入れて打ち上げる。