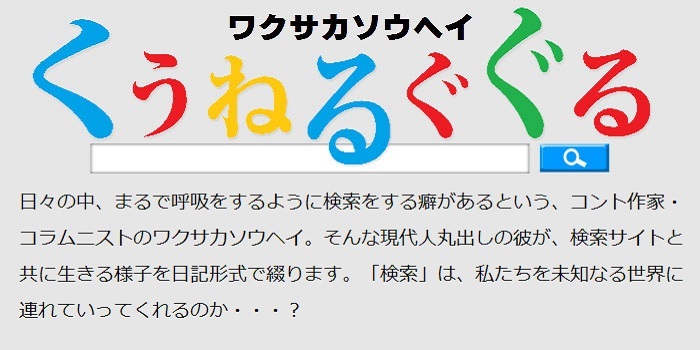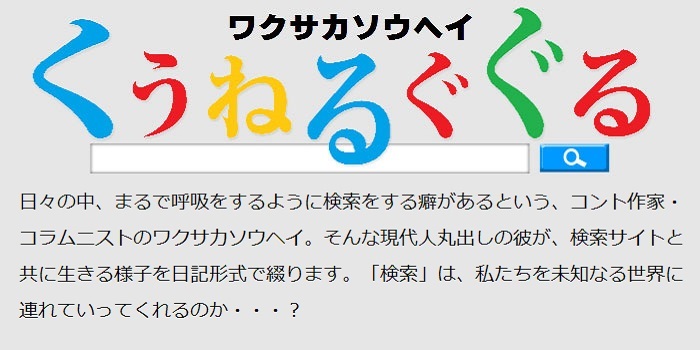第37回:「シャツはシャツでも食べられないシャツ」(後編)
<第37回>
6月×日
【「シャツはシャツでも食べられないシャツ」(後編)】
(前回からの続き。ワクサカさんが小学三年生だった頃に空前のブームに沸き立っていた「いじわるクイズ」。三年一組の教室で起こっていたこととは…)
最初は誰かが始めた、いじわるクイズとも呼べないような、他愛もないひっかけゲームがきっかけだった。
「ねえ、理科、ちゃんと勉強してる?」
「うん、してるよ」
「げー!リカちゃんと勉強してるんだ!」
別にリカちゃんと勉強してたっていいだろ。だいたいリカちゃんって誰だ。このクラスにリカちゃんなんていねえぞ。などといった疑問は鋭く存在していたが、このやり取りが僕たちのクラスで大流行となった。そして次々に亜流のひっかけゲームが発生し始める。
「ねえ、パン作ったことある?」
「うん、あるよ」
「げー!パンツ食ったことあるんだ!」
とか
「ねえ、怖いお話、してもいい?」
「うん、いいよ」
「じゃあ手を握って」
「?」
「お放しっ!(と怖い口調で手を振りほどく)」
とか。
文字起こしをすると、当時のそのひっかけゲームの真の下らなさが身に染みて理解できる。
そしてひっかけゲームブームは、やがて、いじわるクイズブームへと変化していく。
たくさんのいじわるクイズが昼休みの教室内に咲き狂った。
しかし、そのいじわるクイズブームも、やがて飽和状態を迎える。
次々と新しいいじわるクイズが求められるようになる。その過剰需要に応えるために、みんなは放課後、本屋へと走り「いじわるクイズBOOK」なるものを買いあさる。しかし、そんなに種類があるものでもない。結果としてはみんな同じような「いじわるクイズBOOK」を持つことになるので、誰もが答えを知っている状態に陥る。
いじわるクイズのデフレが起きていた。
そんな中、唯一、親からお小遣いというものを貰っていなかったため、「いじわるクイズBOOK」を一冊も所有していない男がいた。
僕である。
そのことに級友たちが気づいた瞬間、ぼくはいじわるクイズの集中砲火を浴びることになる。
「細い道におばあちゃんが歩いていました。そこへトラックが時速100キロで走ってきました。でもおばあちゃんは轢かれませんでした。なんででしょう?」
「大根が10本生えていました。3本抜きました。あと何本?」
「答えがわかっても間違えてしまうクイズです。あなたの頭の中にあるのはなーんだ?」
廊下を歩いているとき。給食を食べているとき。放課後の帰り道。時と場所を選ばず、クラスメイトたちが詐欺師のような顔を浮かべて「さあ、クイズに翻弄されるがいい」とばかりにいじわるクイズを隙間なく出題してくる。
地獄だった。
なんせ、因数分解したところの、「いじわる」な「クイズ」である。意地が悪いことを自ら認めているふてぶてしい態度のクイズを、四六時中浴びせかけられる苦しみ。ご想像いただけるだろうか。
僕は小学三年生にして、軽いノイローゼに陥った。そして親に懇願して、本屋で「いじわるクイズBOOK」を買ってもらった。そこに書かれた回答ページを丸暗記し、次の日、学校に登校した。級友たちは、いつもと同じように腐肉に群がるハゲタカのごとく僕の周りに集まり、次々といじわるクイズを出題してきたが、
「ああ、それの答えは『おばあちゃんが時速101キロで走ったから』だね」
「ははーん、それはつまり『あとは3本(跡は3本)』とでも言えばいいのかな?」
「ウェル・・・。そのクイズの答えを教えてあげよう。『答えはNO(答えは脳)』さ!」
と撃破した。
こうして教室中の熱狂は静まり、いじわるクイズブームは治まった。
僕は胸をなでおろした。ようやく地獄が、終わった。
このあと、「なんかクイズを回答するときの口調がムカついた」という理由で僕はほんのりとイジめられるようになるのだが、それはまた別の機会にお話ししたい。
そんな小学三年生の頃の記憶が電車の中で蘇り、切なくも懐かしい気持ちになる。
いつのまにか、大人になってしまった。いじわるクイズの回答をiPhoneで検索するような、つまらない大人になってしまった。
いじわるクイズに頭を悩ませなくなってから、幾年の月日が流れたのだろう。
目の前に、会社帰りの女性二人組が吊革につかまっていた。完全に目が疲れで死んでいる。
「・・・ねえ、あたしたちの会社って、泥船だよね」
先輩とおぼしき女性が、鉛のような言葉を吐く。
「泥船じゃないですよ」
と後輩の女性が答える。
「え、泥船でしょ」
と先輩が半笑いで返す。
「いえ、泥船ではないですよ。なんだと思います?」
と後輩がまさかのクイズ形式を持ち出してくる。
いじわるクイズか?!大人もまだまだ捨てたものじゃないということを、ここで証明するつもりか?!と僕は聞き耳を立てながら興奮する。
「わからない。泥船じゃないなら、この会社はなんなの?」
先輩に対して、後輩はゆっくりとこう答えた。
「・・・泥ですよ」
大人の世界には、こんなにも辛いクイズがあるだなんて。
目的地に降りると、集団下校の小学生の群れが笑い声を上げながら歩いていた。まるで大人になった僕のことを、笑っているようであった。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)