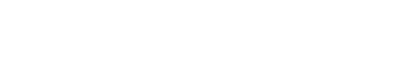和歌山城の天守
外川淳の「城の搦め手」第36回
和歌山城攻めの2日目は、朝から東側を中心にしてバシャバシャと撮影した。
初日の午後に到着し、堀際周辺のホテルで夜景を撮影し、翌日の午前中まで粘るという24時間滞在の撮影スケジュールを想定する。その場合、城の縄張図をよく見て、夕方は西側中心、朝は東側中心という撮影計画を立てると、太陽と喧嘩せずにすむ。逆光補正の性能も向上したものの、やはり順光の方が普通にいい写真が入手しやすい。

岡口門と天守
9:17撮影。午前中の光により、ほどよい感じカット。早く眠って起きられれば、朝日を浴びるカットにしたかったが、昨晩は寝つきが悪く、行動開始は8時となる。和歌山城の魅力として、天守曲輪の復元建築群に加え、壮大な石垣群も忘れてはならない。
さて、石垣の撮影方法は、簡単なのか、むずかしいのか、いまだによくわからない。だいたい石垣は、陽光に照らされることなく、色彩も限定される。

山麓部南側の石垣
コーナーの算木積みをカット内に組み込むのは、石垣撮影の王道。石垣は樹木に囲まれ、光量不足というパターンが多いのだが、松の丸の櫓台石垣は順光のよい写真が撮影できた。

櫓台というより天守台に等しい規模を誇る。

ほぼ同じ地点から、下からあおって撮影したカット。石垣と青空の露出適性に開きがあり、なかなか決まらなかったが、ようやく納得のカットとなる。かつて、このようなアングルで撮影するためには、戦場で兵士が伏せ撃ちをするように、地面に仰向けになってカメラを構える必要があった。
現在では、カメラのファインダーが可動すれば、中腰の状態で、対象物を下からあおることができる。いずれにしろ、誤解のうけやすい姿勢での撮影のため、人波が途絶えたのを確認する必要が高い。次回も、和歌山城ネタが続く予定。