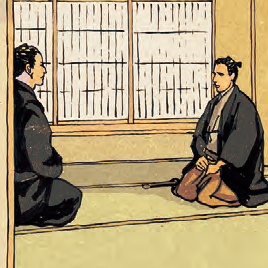西郷隆盛は征韓論者ではなかった
政治改革を断行するも志半ばで挫折
◆遣韓論を唱えた西郷は征韓論者の代表と見られた
この明治4年は、新政府が大規模な節団を欧米に派遣した年でもあった。特命全権大使は岩具視で、副使に大久保利通、木戸孝允、伊藤博文。その間の留守を預かったのは三条実美(さねとみ)、西郷隆盛、大隈重信、板垣退助らだ。
この時、使節団組と留守政府は取り決めを交わしていた。新たな政策などは、使節団が帰国した後に審議する、という内容だ。
「しかし国内は、廃藩置県に伴うさまざまな混乱や、放置しておけない施策が目白押しでした。結局、使節団側は留守政府が必要な政策を進める権限を認めました。そこで西郷が中心となり行われたのが徴兵制の導入、地租改正、学制の制定という3大改革です」。
しかし、まず人事で使節団組と西郷の溝ができた。徴兵制に関して近衛(このえ)兵と対立していた山県有朋(やまがたありとも)に代わり、西郷は自らが「近衛都督(このえととく)・参兼陸軍元帥」に就任。後藤象二郎や江藤新平らを登用した。これに発した井上馨が官を辞したので、留守政府中枢を佐賀や土佐の出身者が占めたのである。
それに加え朝鮮との関係も両者の間に亀裂を生んだ。日本が維新を迎えると、朝鮮は「夷狄(いてき)と国交を結んだ」と日本を拒絶した。この朝鮮の態度に、板垣退助らは軍事行動を含む強硬政策を訴えた。それに対して西郷は「軍隊は使わず、しかるべき者が使者に立つべし」と反論。そして「使者には自分が立つ」と訴え、その案が閣議決定された。
「西郷は征韓論者だと誤解されがちですが、実際は遣韓(けんかん)論を唱えています。板垣へ送った手紙に“自分が殺されたら攻めればいい”と記したことが誤解の原因でしょう。ロシアの脅威を意識していた西郷には、朝鮮や清国の関係を強化し、列強に対抗するという思惑があったと考えられます」。
ところが明治6年(1873)、使節団組が帰国すると揃ってこれに反対を唱えた。大久保は参議を辞任すると言い、岩倉具視は閣議決定を無視して朝鮮使節派遣の延期を上奏すると言う。怒った西郷は辞表を提出したのである。
- 1
- 2