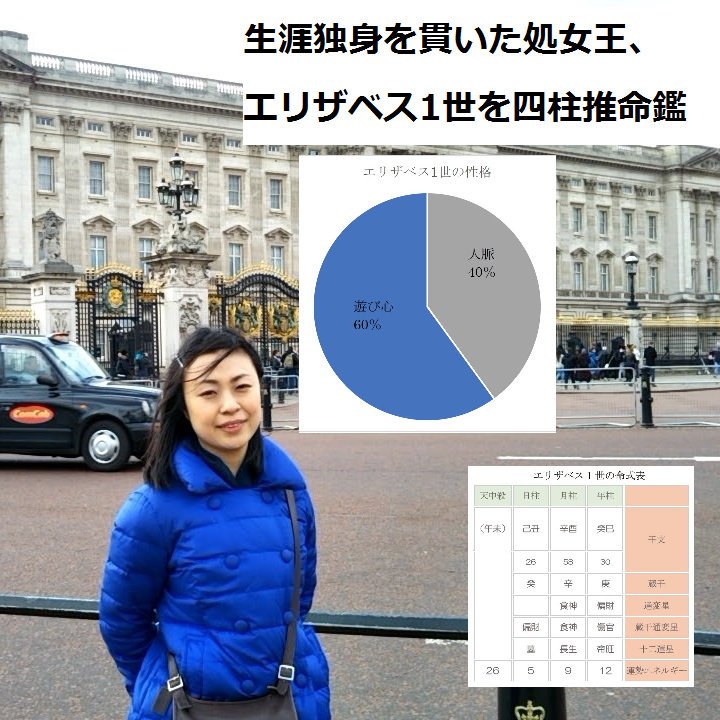時代や社会が見えてくる世界のミイラ文化
地域文化の中で死生観や人生観を形成してきた
人類はいつも死者への尊敬と恐れの間で動揺してきた

世界には昔から様々な埋葬習慣がある。現在の日本では火葬して墓地に納骨し、法事の時や故人への思いを偲ぶ際に、お墓を訪れるといったことが主流だろう。
しかし人類史においては風土環境の違いから、古今東西多様な埋葬習慣と埋葬文化があったのは言うまでもない。
春夏秋冬や山川草木の変化、火山噴火や地震、津波、台風といった自然災害と、環境の激変がもたらす風景のバリエーション。
そうした自然環境の中で、私たち日本人の諸行無常といった人生観や死生観、埋葬文化といったものも自然に形成されてきた。現在の日本人があたり前と考えている火葬にしても、それは死者に対する冒涜であり、遺体の破壊行為であると見る文化もある。20世紀初頭のドイツの人類学者レオ・フロベニウスは、「人類はいつも、死者への尊敬と恐れの間で動揺している」と言う言葉を残している。
そして、あらゆる葬式の習慣も「死体の破壊と保存との間を動揺している」と言っているのだ。
ある日突然、別れ難い大切な家族を失って呆然とする時、私たちはその死を認めたがらず、ずっとそのまま何事もなかったように、これまでの生活を続けようとする思いがある。
幼い我が子を亡くした母親が、その子をずっと抱き続け、これまでと同様食事を与え、語りかけ、子守唄を歌ってやる。
そんな悲痛な母親の姿を見る時、周囲はひとまず傍観するしかないこともあるだろう。
しかし季節によって、あっと言う間に腐敗が進み、病原菌の発生や悪臭を放ち始める日本の気候では、いずれ誰かが母親を諭し、醜く変化していく前に遺体から引き離し、保存や管理のしやすい状態へと手を加えるしかない。
そのために愛しい子供の遺体であっても、火葬という破壊行為をせざるを得ないのだ。
もっとも日本の埋葬習慣は、元来土葬が主流だったが、これにしても死体を土に埋めることで、様々な虫や細菌、バクテリアなどが徐々に遺体を蝕み、骨と化して行く道をたどる。つまりゆっくりとした破壊行為には違いない。
ところが世界には、死後もずっとそのままの姿で形をとどめ、何百年、何千年と遺体が腐敗や破壊から免れるような環境も存在する。
そのひとつが極端な乾燥により、死後もずっと保存状態が続いてミイラと化した遺体である。
そのようなミイラが自然にできる乾燥気候の地域では、自ずと死者への思いや死生観、埋葬習慣といったものも変わらざるを得ないだろう。
古代アンデス文明では、ミイラは死後もずっと家族と共に暮らし、食事を共にし、語り合ったりする習慣があった。
時にミイラは家族の相談相手となり、死後もずっと家族の中で存在し続けるのだ。
そしてまた同様に乾燥砂漠地帯として有名なエジプトでも、独自のミイラ文化が3000有余年にも渡り続けられてきた。
人々は昔から「不死」への願望を抱き続け、「復活」や「再生」、そして肉体が消失した場合には、
「魂の不滅」といったものを信じてきた。
人間は誰でも、いつ死ぬかわからない。その恐れや不安から逃れるための心理として、様々な宗教や埋葬文化も必要とされた。
エジプトにおけるミイラは、遺体をミイラ化することによって、死者がその死後も、個人的な“永遠の命”を得るための拠点として作られた。
それにより生前叶わなかったことや、苦しかった病などからも逃れ、平和で幸福な世界があることを願ったのだ。
- 1
- 2
KEYWORDS:
教養としてのミイラ図鑑 ―世界一奇妙な「永遠の命」
著者:ミイラ学プロジェクト

「死」を「永遠の命」として形にしたミイラ。いま、エジプトはもちろん世界各地で、数多くのミイラが発見されており、かつミイラの研究も進んでいる。実は知っているようで知らないミイラの最新の研究結果とこれまでにないインパクトのあるビジュアルで見せたのが本書。高齢化社会の日本ではいま、「死」は誰にとっても身近にして考えざるを得ないこと。「死」を永遠の命の形として表したミイラは私たちに何を語りかけてくるのか? 人気の仏教学者の佐々木閑氏、博物館学者の宮瀧交二氏、文化人類学に精通する著述家田中真知氏の監修と解説とコラムで展開する唯一無二の「中学生から大人まで」楽しめるミイラ学本。