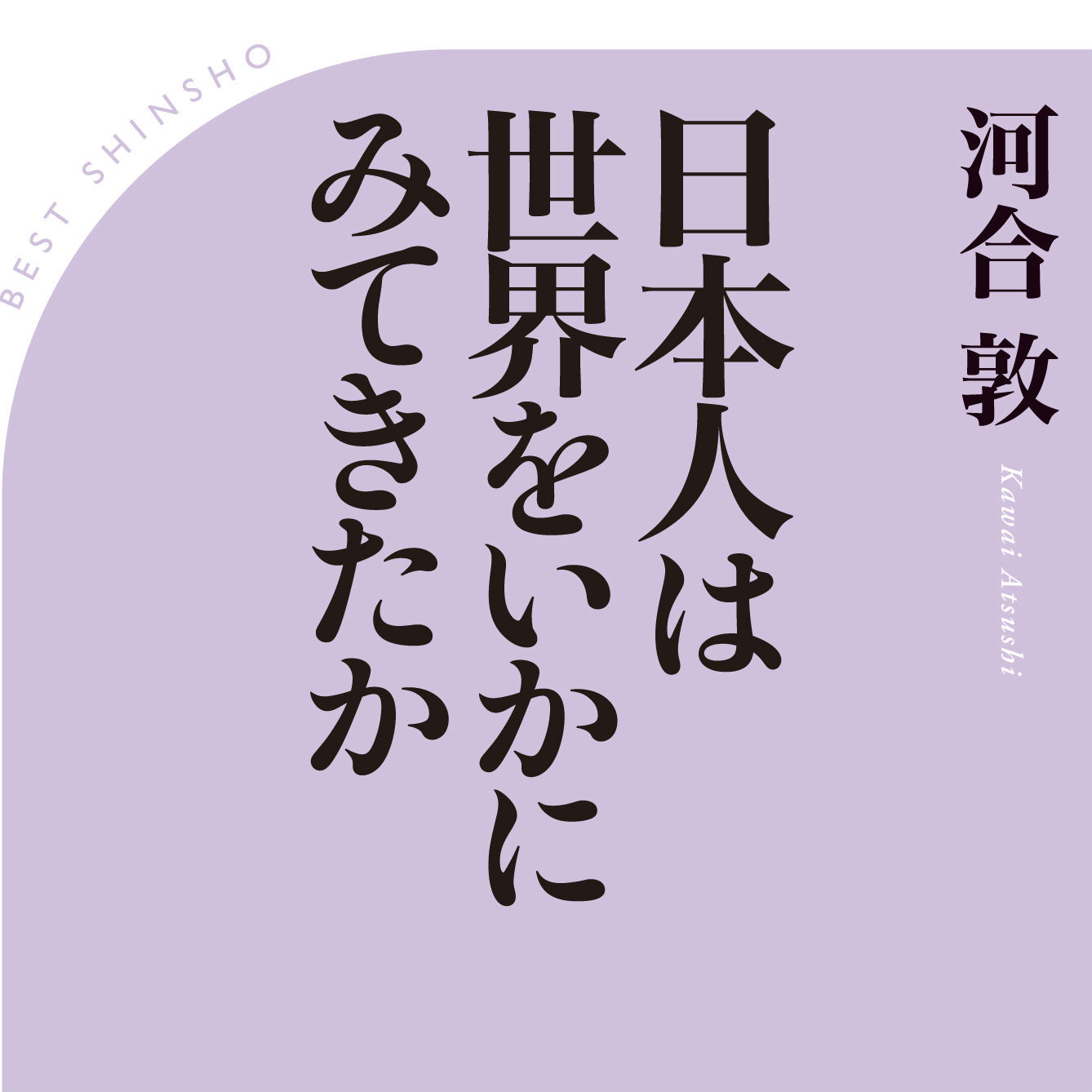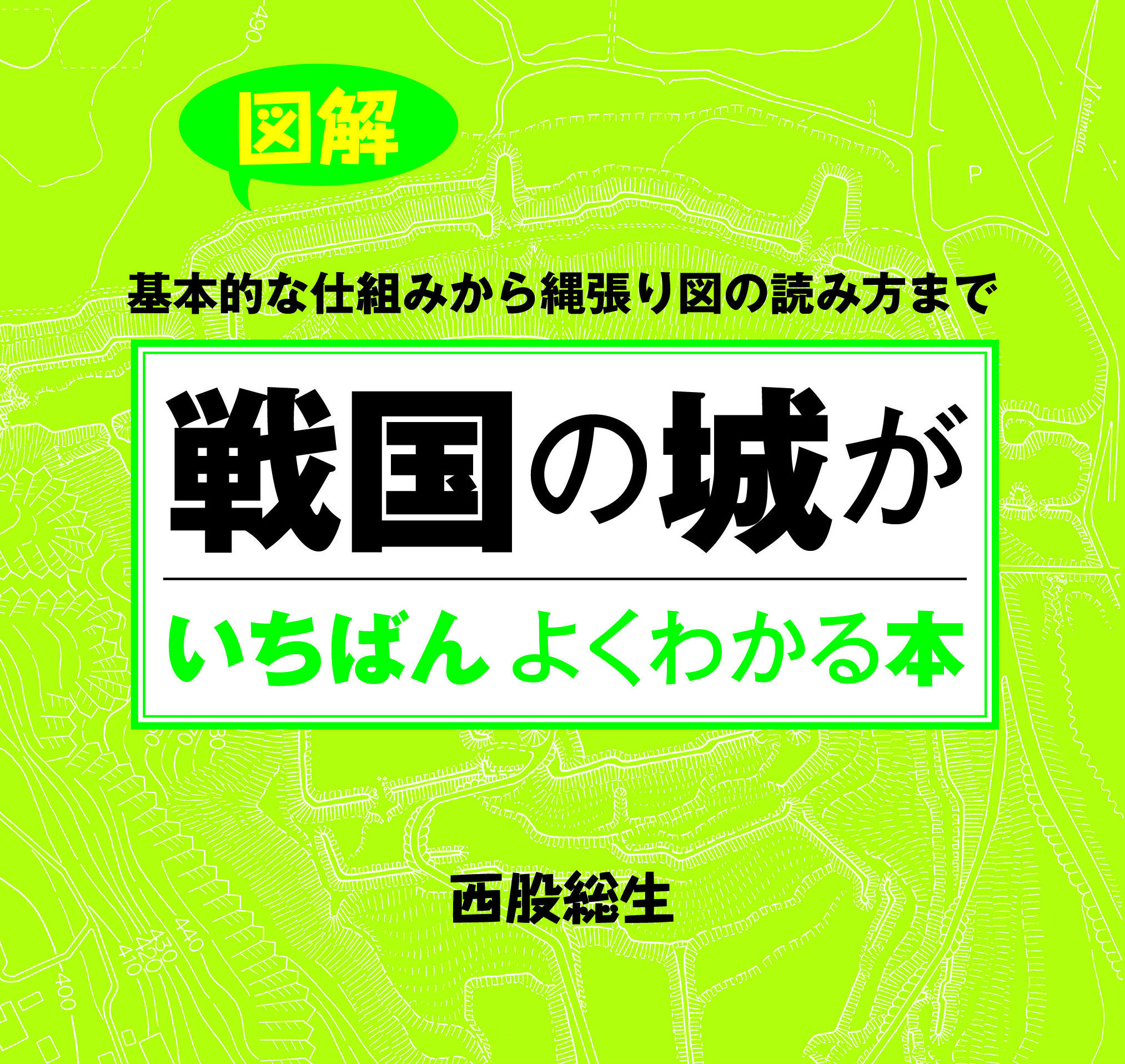江戸の粋「江戸切子づくり」を体験しよう!
匠の技を職人に教えてもらう伝統工芸品づくり
歴史に親しみ、ものづくりの楽しさを味わうため、
技を極める伝統工芸品づくりをぜひ体験してみよう!

色被せガラスを削って仕上げる多彩な紋様が魅力だ。写真は、赤と黒の市松紋が現代的な「すみだモダン」粋と技シリーズのグラス。

オランダから伝わったガラス製品に施した切子細工
透明なガラスの外側に藍や赤の色ガラスを着せて形づくられた器を削り、さまざまな文様を施した江戸切子。江戸の天保年間(1830〜1844)、江戸大伝馬町でビードロ問屋を営む加賀屋久兵衛らが、オランダをはじめヨーロッパから伝わったガラス製品に切子細工を施したのが始まりと言われている。
当時は、無色透明なガラス製品のみだったが、明治に入ってから現在のような色被せガラスも使われるようになった。その後、道具の機械化により高度な技も生まれ、今に伝わる宝石をちりばめたように美しく繊細な切子細工の製品がつくられるようになる。

熟練の技で切子細工を施すのは、すみだマイスターの川井更造さん。
〝江戸切子〟の名は、昭和59年に東京都伝統工芸品に指定されてから。その後は地域のブランドとして定着し、若い職人に技術を伝え、育成している。東京スカイツリー開業時には、ソラマチ商店街の全店舗に江戸切子を使った行灯風の看板が使われ、一気に注目度も高まった。
体験では、色被せグラスに伝統的な紋様を削り出し、オリジナルグラスをつくることができる。好きなデザインを考え、天然の砥石やダイヤ粒を練り込んだステンレス円盤でグラスを削る作業は、なかなかスリリングで楽しい。10時30分、13時30分、15時30分の一日3回。

左/さまざまな色や形のグラスから好きなものを選び、デザインを決め、削る際の目印になる線を描く。右/きれいに紋様を削り出すためのコツを教えてもらいながら、ステンレス円盤でグラスを削る。
すみだ江戸切子館
住東京都墨田区太平2-10-9
☎03-3623-4148 要予約
営)10時〜18時 休)日曜・祝日
料4320円〜 所要時間1時間30分