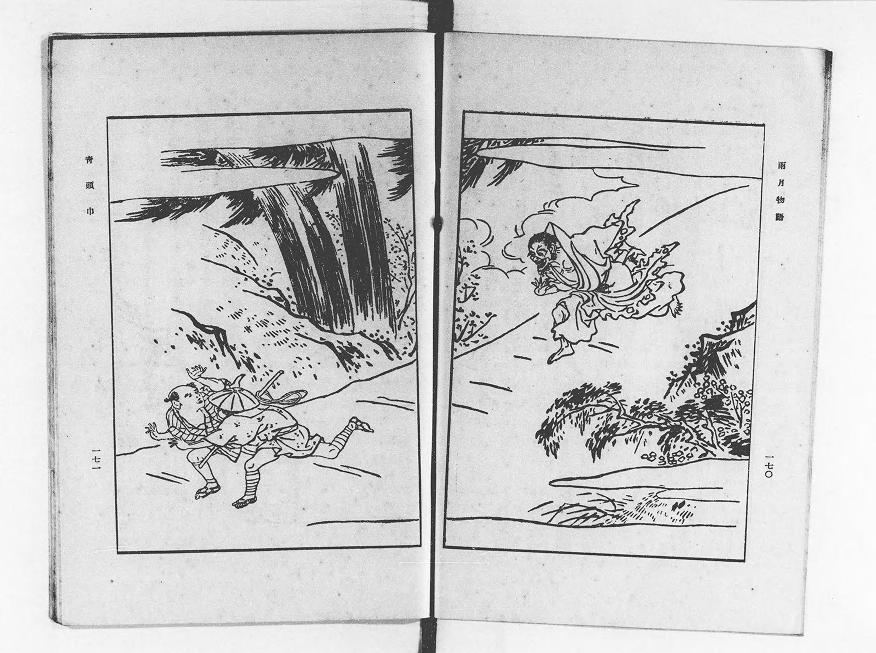子どもをありのままに育てる怖さ
新学期シーズン必読。混迷する教育現場の原因を探る。
◆子どもはなぜ変わったか

子どもの養育(家庭)や教育(学校)が困難になってくると、教育の仕方やあり方が議論されるようになる。「農業社会的近代」までは親もおとなも教師も自信を持って子どもの教育にあたっていた。昔と同じようにやればよかったからである。「産業社会的近代」に入って、子どもが共同体的なものから自立し始め、養育も教育も揺らぎ始める。これは近代社会(個人の自立)にともなう必然的なものである。社会が構造的に変わっていくので、子どもも変容し始め、親や教師に自信や確信がなくなったのである。
そして1970年代後半からの「消費社会的近代」に入ると、養育や教育は困難になり始める。日本の近代的個人には「普遍的なるもの」(たとえば、ヨーロッパのキリスト教のような)の媒介がないので、本人がそう思えばすでに立派な個人(人間)を主張できるからである。
近代的個人にはどういう力量や資質が求められるのか、などと誰も考えない。本人がそう思えば個人なのである。どういうひとのあり方が近代的な個人や社会的な個人としての条件を満たすのかという発想がない。戦後の教育には「個人を育てる」はあっても、個人と「普遍的なるもの」や国家や社会との接点がどうあるべきかという観点がなかったからである。だから、「消費社会的近代」に入ると自己利益の追求者が個人となり、個人が内面化すべき社会性や国家性や普遍性がほとんど問われなくなったのである。「そこに居る」個人が絶対的になった。つまり、自分の考え方が絶対になった。
そうして、子どもの育て方や教育の仕方についての議論が出てくる。教育議論は大きくいえば教育主義と放任主義とに分かれる(但し、現在のアカデミズムなどでの議論はもっと複雑で入り組んでいる)。もちろん、戦後の保守は教育主義的であり、革新は放任主義的であった。保守は教育には国家性が必要だと考え、革新は子どもそのものに成長の可能性があり、また、教科(科学)の体系が近代的個人を人間的、道徳的に形成すると信じていた(道徳的教育不要論である)。
- 1
- 2