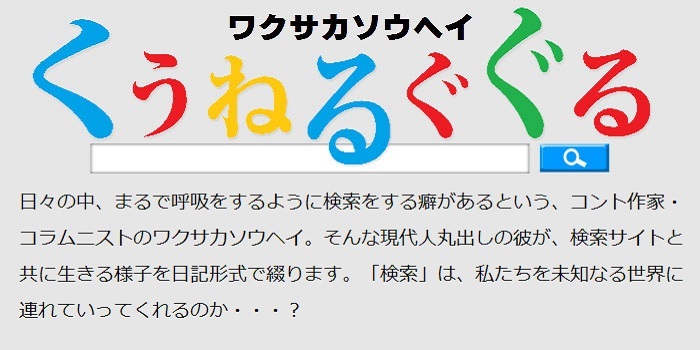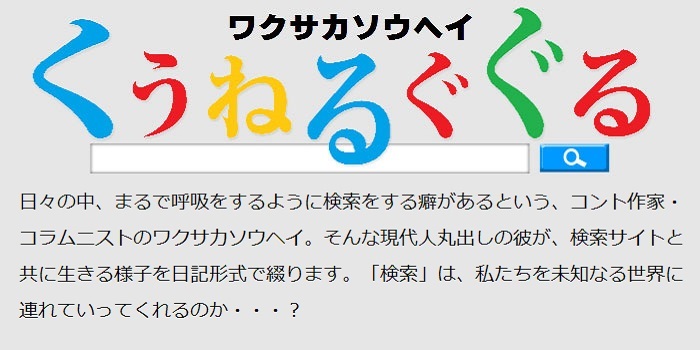第69回:「銀座 BAR」「神楽坂 BAR」
<第69回>
2月×日
【「銀座 BAR」】
東京へと遊びに出てきた友人Sと会う。
Sは普段、かなりの辺境に住んでいる。彼の家の前の畑では、昼夜問わずカエルとウサギが飛び跳ねているという、「鳥獣戯画の実写版」みたいな光景が広がっているらしい。
そのSと銀座で待ち合わせ。どこか行きたい場所はあるかと尋ねると、「東京のBARに行きたい」などとSはのたまう。「知ってるBARに連れていけ」と。
ふざけるな。東京在住の人間が誰でもBARに詳しいと思ったら大間違いだ。「鳥貴族」に連れていってやるからそれで満足しろ。などと抗弁したものの、Sは「BAR!BAR!BAR!」などと喚きたて、一歩も引かない構えである。まったく困った青春18切符野郎である。
しかたがない、BARに連れていってやるか。僕は諦めた。それにこちとら腐っても、東京都水道局の産湯に浸かり、東京FMを子守り唄がわりに聴き、東京ガスの灯で寒い冬を何度も乗り切りここまで大きくなった、生粋の東京人間である。ついこの間まで夜這いの風習が残っていた村に住んでいるSに、ナメられては困る。BARのひとつやふたつ、案内してやろうではないか。
と言っても、ここは銀座。おとなしく「銀座 BAR」で検索。食べログの情報を頼りに、近くにあるBARへとおそるおそる二人で入店する。
一枚板の格調高いカウンター。耳に柔らかいJAZZ。ランプが作る優しい薄明かり。
それは、普段「大きな靴流通センター」とか「大きなイオン」とか「大きな蟻」とかしか見ていないSにとって、異空間であった。
それはまた、普段スマホで無課金のゲームばかりやっている僕にとっても、異空間であった。
BARの中央に掲げられた剥製の鹿の首が、こちらに向かって「カエレ、カエレ、バチガイナニンゲン、カエレ」と言っているのが聞こえた。
身の丈にまったく合っていない空気に圧倒され、二人は会話なく酒をすすった。
そしてそのまま会話なく店をあとにし、会話のないままSは東京駅から新幹線で地元へと帰っていった。
BARなんか行ったばっかりに、時間をドブに捨てることになった。
Sの静かな後ろ姿を見送りながら、「BAR!BAR!BAR!」と元気いっぱいに叫んでいた頃の彼が、早くも懐かしかった。
2月×日
【神楽坂 BAR】
神楽坂にて取材。同行の担当Hさんと、取材後に軽く飲むことに。
「BARにでも行きますか」と、Hさん。
またもやBARである。うろたえる僕。しかし「ああ、BARですか。墓参りの帰りに、よく家族で行ったっけ」などと嘯いて、なんとか余裕を取り繕う。
二人で「神楽坂 BAR」を検索し、神楽坂の細い路地を迷いつつ、一軒のBARを発見する。
おそろしいほどに「大人」な雰囲気が漂う店内。僕のような、いまだに文房具店の試し書きコーナーで「うんこ」と書いてしまうような人間が、果たして席に着いていいものなのか。
注文を聞かれる。緊張の一瞬だ。なにを頼めばいいのか。するとHさんがサラッと「飲み口の軽いものをください」と注文。「かしこまりました」とバーテンダー。おお、かっこいい。なんだ、こうやって注文すればいいのか。すかさず真似をして、
「僕も飲み口の軽いものを」
とオーダーした。
するとバーテンダーが
「甘くないほうがいいですか?」
と聞いてきた。あれ?なぜ「かしこまりました」と言ってくれない…?
「えっと…甘くないのがいいです」
「なるほど。強めでもいいですか?」
「あ、えっと、強くもなく、弱くもなくでお願いします…」
「ふむ。ベースのご希望はありますか?」
なんだ。なんなんだ。なんで僕だけQ&Aコーナーが発生してるんだ。そのあとも次々と質問を繰り出してくるバーテンダー。その質問に対して僕は
「えっと、とにかく太平洋のように優しい味で」
「どんなに臭いお酒を出されても大丈夫です、長男なんで」
「簡単にいうと梅干しサワーみたいなやつを」
などと勘だけで答え続けた。起きながらにして、寝言を喋っているような時間だった。
一連の質疑応答があったのち、バーテンダーは困ったような笑顔を浮かべて、
「お客様のご要望に合うお酒は、この世に存在いたしません」
と言い放った。
その時の僕の顔は、暗い店内でもはっきりと分かるほど、真っ赤だったはずだ。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。お楽しみに!【バックナンバー】
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)